新聞界を揺るがす告発本『小説 新聞社販売局』~著者・幸田泉氏にインタビュー
-

-
新聞界を揺るがす驚天動地の”告発本”が、いま話題になっている。『小説 新聞社販売局』(講談社)。著者の幸田泉さんは全国紙の元社会部記者だ。社内で販売部門への”左遷”も経験している。八重洲ブックセンター(東京)のフィクション・チャートではベスト10に入り、新聞記者たちが多く集まるジュンク堂プレスセンター店でもチャートイン。9月9日に発行されたばかりだが、早くも増刷が決まった。本書の反響次第では、ひょっとしたら日本経済最後の”不良資産”といわれる新聞の押し紙問題に重大な局面が生じるかもしれない。著者の幸田さんに都心のホテルでインタビューした。
(聞き手:ジャーナリスト・会澤正視)
――たいへん話題になっていますね。『小説 新聞社販売局』を書かれた動機というのは、どういうものだったのでしょう。
幸田泉氏(以下、幸田) 新聞社に記者として入社した私は、社内では「編集局育ち」でしたが、販売局に配属されて初めて新聞の販売現場を知って、ものすごく衝撃を受けました。週刊誌からの取材や販売店主に訴えられた裁判など、新聞社の「押し紙」が公の場に出る時、新聞社は「押し紙なんかありません」と言っておきながら、実は相当の量の「押し紙」が存在しているのです。いわゆる「公称部数」と言われている部数は、少々、水増しされているのだろうと思ってはいたのですが、現実は自分の予想をはるかに上回る規模でした。新聞社が印刷して販売店に卸している新聞のうち、お客さんの手元に届いている部数は、販売店によって違うのですが、実態的には5割~7割ぐらいだと思います。
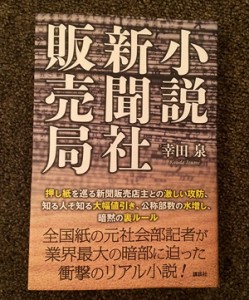 販売局の所属になってこの深刻な実情を知るほどに、私の気持ちはどんどん憂鬱になりました。社内では中間管理職的な立場だったので、周りへの影響も考えて、職場では内心の思いを顔に出すことはなるべくしませんでしたが、毎日、気分はとても憂鬱でした。販売局に異動して2年後、編集局に戻るという異動の打診があったのですが、もはや私の憂鬱は「編集局に戻れたらいいや」で収まるレベルではありませんでした。こんなひどい押し紙の実態を見てしまった……、それを見て見ぬふりをして、定年まであと10数年間、何事もないかのように仕事を続けていかなければならないのか……。
販売局の所属になってこの深刻な実情を知るほどに、私の気持ちはどんどん憂鬱になりました。社内では中間管理職的な立場だったので、周りへの影響も考えて、職場では内心の思いを顔に出すことはなるべくしませんでしたが、毎日、気分はとても憂鬱でした。販売局に異動して2年後、編集局に戻るという異動の打診があったのですが、もはや私の憂鬱は「編集局に戻れたらいいや」で収まるレベルではありませんでした。こんなひどい押し紙の実態を見てしまった……、それを見て見ぬふりをして、定年まであと10数年間、何事もないかのように仕事を続けていかなければならないのか……。仮に私が社内で声を上げて「押し紙をやめましょう」と改革を訴えたところで、絶対に受け入れられないでしょう。「お前がそんなことを言う立場にない」と言われて無視されるに決まっています。結局、会社にいても自分の力で解決することはできないんです。この深刻な問題を抱えたまま、これ以上、会社で働き続ける気にはとてもならなくて、退職の道を選びました。
≪著者の幸田さんは1965年、大阪生まれ。大卒後、89年に全国紙に入社し、地方支局勤務後、大阪本社社会部で大阪府警、大阪地検、大阪地高裁などを担当。東京本社社会部でも警察庁や遊軍を経験し、再び大阪本社社会部に異動。その後、管理部門を経て大阪社会部のデスクに。
このデスク時代に大阪地検特捜部の証拠改竄事件が発生。往時の従軍記者のように検察に唯々諾々として戦果を書き立てるばかりの、これまでの検察報道に疑問を呈する原稿を執筆したところ、事件記者上がりの大阪本社編集局長が激怒。幸田さんは社会部デスクを1年で外され、そのまた1年後、販売局に異動させられることになった。このあと2年間の販売局勤務で見聞きしたことをベースに書かれたのが『小説 新聞社販売局』である。同書は、膨大な押し紙の存在が新聞販売店の経営を圧迫していることを、販売現場で知った情報をもとに迫真のタッチで描いている≫
――なぜ小説という体裁をとったのでしょう。ノンフィクションという手法は考えなかったのですか。
幸田 もともと小説を書きたいという気持ちを漠然と持っていました。ノンフィクションノベル的な原稿にして、世の中で起きていることをわかりやすく伝えたいと思っていました。会社を辞めた時、新聞販売の問題点は私にとって最も重要なテーマでしたが、これを書いたら出身の新聞社や販売店に迷惑がかかるのではと踏ん切りがつかず、半年ぐらいは執筆したり中断したりを繰り返していました。でも、自分にとって一番やりたいことを脇に置いて他の原稿を書いていても、自分の人生を生きている気がせず、「やはり書くしかない」と心を決めました。このテーマを作品に仕上げて乗り越えなければ、私は作家としての第一歩が踏み出せないと思ったんです。
ジャーナリストや新聞販売店主が書いた押し紙問題を告発するものはあるのですが、広く読まれているとは言い難い。そこで、小説にした方がむしろ読まれるとも考えました。
≪新聞社は販売店に卸す部数を、実際の販売部数とはかかわりなく決めているため、販売店には売れ残る新聞が山積みになっている。たとえば1,000部しか売れていない地域の販売店に本社が2,000部を割り当てて卸すと、販売店主は2,000部分の代金を入金しなければならない。販売店の経営に必要な収入に不足が生じると、不足分は本社からの販売補助金という形で補填するのだが、つるべ落としに部数が減少する現在の販売現場では、それでも販売店の収支があがなえない。そのため本社への納金期日に全額の入金ができない販売店が出てくる
同書は、販売店からの販売収入の集金に四苦八苦する新聞社販売局の担当員の姿が描かれている。販売店が納金期日までに入金できないと、担当の販売員が不足分を肩代わりして自己負担することが恒常化しているという≫
――実際に読んだ人は、ここに書かれたことはすべて事実なのではないかと受け止めると思うのですが、どこまでが事実で、どこからがフィクション(虚構)なのでしょうか。
幸田 私が一番、問題にしたかった販売の構造的な問題はかなりリアルに描いたつもりです。販売店が納金できないので、不足分を担当員が立て替えているとか、その立て替えのためにした借金が結構な金額で残っているという話は、実際に販売局で耳にした話です。部数の水増しという会社の方針が、こんな形で現場の担当員にしわ寄せがきているとは、本当に気の毒だと思いました。入金率を守ろう、会社を守ろうと真面目になればなるほど追い込まれるなんて悲劇じゃないですか。
販売店の積立金を私的に使い込む担当員の話が本書に出てきますが、あの不祥事のデパートのような人物にも実在するモデルがいます。でも、使い込んだのではなくて入金不足を穴埋めするのに使ったとか、妙な言い訳を許すことになってしまい、社内調査は難航していました。
ABC協会が販売店に部数調査に入ることがあるのですが、調査に来る日取りはあらかじめわかるので、調査対象の資料を都合のいいように改竄するということも聞きました。別の新聞社の系列販売店主らが出版した書籍にもそういう話が書かれていて、やはりどこでも同じなんだとつらくなりました。
――まるで不良債権をごまかしたい銀行が、MOF担を通じて旧大蔵省の金融検査の日時を事前に探り、それにあわせて資料を隠蔽したりするのと似ていますね。
幸田 同じです。いままで押し紙を告発するノンフィクションは、主に経営難に陥る販売店サイドから描かれたものが多かったと思うのです。新聞発行本社が無理やり販売店に新聞をたくさん買わせている、という構図です。
でも、もはやそういう問題だけではなく「これは確実に新聞社の経営に跳ね返ってきている」と思うようになってきたのです。いまの新聞社は本当の実売部数がわからないから、正確なマーケット調査すらできない。だから新聞社では販売局が「伏魔殿」と言われるんです。販売局にいた時、編集局など他の部署の人たちから「販売のことなんて分からないから」とよく言われました。「何かカラクリがあるんだろうな」と薄々はわかりつつ、見て見ぬふりをして、詳しく知ろうとしないし、本心は「知りたくない」のでしょう。一方、販売局のほうも本当の「闇」は他の部署には見せない。たぶん、新聞社では社員も経営陣も「闇」を守ることが、会社を守り、新聞というジャーナリズムを守ると信じています。私は小説のなかで言いたかった。「本当に会社を守ることにつながっていますか?」と。
≪編集偏重の新聞社では、販売局は販売プロパー社員たちの”聖域”となっている。販売局は本当の実売部数を明らかにせず、本社が販売店に卸している部数しか情報開示しない。押し紙とセットになっている販売店への補助金の仕組みは複雑で、販売局以外の人間はなかなかうかがい知れない。販売局員は、部数が伸びていた販売好調時には経費の流用など”甘い汁”を吸ってきたこともあり、販売局以外の社員に対しては非常に排他的・閉鎖的だ。私的流用など不祥事をおこした社員も内部で抱え込み、問題を顕在化させたがらない≫
――古巣を含めて反響はいかがですか?
幸田 古巣のなかでは私の小説の出版が「暴露本を書いた」という話で広まっているようです。直接のクレームや抗議はありませんが。古巣のなかでも個人的に親しかった人たちは「面白かった」と言ってくれています。暴露本という観点ではなく「企業小説として面白い」「自分も頑張ろうと勇気づけられた」という感想をもらったのもとてもうれしいです。新聞販売に対して問題提起するだけでなく、組織のなかで働く人たちの喜怒哀楽に寄り添って応援する小説にしたいと思っていましたので。
(了)
関連記事
2024年4月8日 14:102024年4月3日 15:002024年4月1日 17:002024年4月18日 10:452024年4月15日 17:202024年4月5日 17:402024年4月18日 10:45
最近の人気記事
まちかど風景
- 優良企業を集めた求人サイト
-
 Premium Search 求人を探す
Premium Search 求人を探す
- 業界注目!特集
-
 産廃処理最前線
産廃処理最前線
サステナブルな社会を目指す
- MAX WORLD監修
-
 パーム油やPKSの情報を発信
パーム油やPKSの情報を発信
パームエナジーニュース







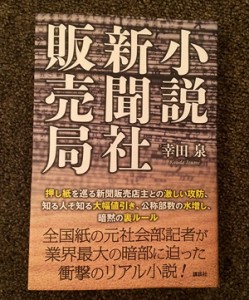 販売局の所属になってこの深刻な実情を知るほどに、私の気持ちはどんどん憂鬱になりました。社内では中間管理職的な立場だったので、周りへの影響も考えて、職場では内心の思いを顔に出すことはなるべくしませんでしたが、毎日、気分はとても憂鬱でした。販売局に異動して2年後、編集局に戻るという異動の打診があったのですが、もはや私の憂鬱は「編集局に戻れたらいいや」で収まるレベルではありませんでした。こんなひどい押し紙の実態を見てしまった……、それを見て見ぬふりをして、定年まであと10数年間、何事もないかのように仕事を続けていかなければならないのか……。
販売局の所属になってこの深刻な実情を知るほどに、私の気持ちはどんどん憂鬱になりました。社内では中間管理職的な立場だったので、周りへの影響も考えて、職場では内心の思いを顔に出すことはなるべくしませんでしたが、毎日、気分はとても憂鬱でした。販売局に異動して2年後、編集局に戻るという異動の打診があったのですが、もはや私の憂鬱は「編集局に戻れたらいいや」で収まるレベルではありませんでした。こんなひどい押し紙の実態を見てしまった……、それを見て見ぬふりをして、定年まであと10数年間、何事もないかのように仕事を続けていかなければならないのか……。
























