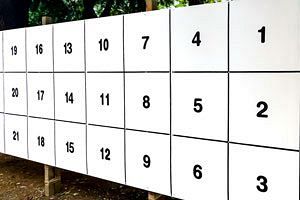今日本で、世界で求められる文系の知!(4)
-

-
東京大学大学院情報学環教授 吉見 俊哉 氏
最も基本的なことは「文系」=「教養」ではない
――少し話を転じます。先生は、今回の「文系学部廃止」反対論議の中で、国民、有識者(学者を含めて)、経済人(経団連など)など、使われていた言葉に混乱があったことをご指摘されています。その点を解説していただけますか。
吉見 それは、「文系の知」をご理解いただくためにも、大切なことなので簡単にご説明します。まず、最も基本的なことですが、「文系」=「教養」ではありません。理系も、文系も専門知があります。そして、その専門知に対して教養知があるのです。ですから、「文系学部を廃止するとは何事だ。教養教育は必要である!」という論の立て方は誤りです。つまり、理系、文系というカテゴリーと専門、教養というカテゴリーは別物なのです。
リベラルアーツは文系、理系、芸術系で構成する
次に、「リベラルアーツ」、「教養」、「一般教育」という言葉を順にご説明致します。
 出自が一番古いのは、キリスト教世界を背景にしたリベラルアーツです。これはもともと、ヨーロッパ中世の12、13世紀に誕生した大学における自由7科(文法学、修辞学、論理学、代数学、幾何学、天文学、音楽)のことを言います。このリベラルアーツは、当時「有用な学」と言われた、神学(神の役に立つ)、法学(国家の役に立つ)、医学(人の役に立つ)と対比されていました。その構成は、文系・理系・芸術系で、3:3:1になっています。今回の一部の報道では、リベラルアーツ=文系と考えているような発言もありましたが、それは誤りです。リベラルアーツの半分は理系なのです。この自由7科はその後、哲学になっていきます。哲学者のデカルト(解析幾何学の原理を確立)やライプニッツ(微積分法を発見)が同時に数学者であったのはごく自然のことだったのです。
出自が一番古いのは、キリスト教世界を背景にしたリベラルアーツです。これはもともと、ヨーロッパ中世の12、13世紀に誕生した大学における自由7科(文法学、修辞学、論理学、代数学、幾何学、天文学、音楽)のことを言います。このリベラルアーツは、当時「有用な学」と言われた、神学(神の役に立つ)、法学(国家の役に立つ)、医学(人の役に立つ)と対比されていました。その構成は、文系・理系・芸術系で、3:3:1になっています。今回の一部の報道では、リベラルアーツ=文系と考えているような発言もありましたが、それは誤りです。リベラルアーツの半分は理系なのです。この自由7科はその後、哲学になっていきます。哲学者のデカルト(解析幾何学の原理を確立)やライプニッツ(微積分法を発見)が同時に数学者であったのはごく自然のことだったのです。「教養」は国民国家にとって基礎的な知として誕生
次に、「教養」ですが、その出自は、18世紀の後半から19世紀にかけてです。ドイツ(プロイセン)を中心に国民国家が生まれてきた時に、国民国家にとって基礎的な知「文化=教養」として生まれています。哲学者カントはその先駆者ですが、フィヒテ、ヘーゲルといったドイツ哲学の興隆があり、文学ではゲーテ、シラー、音楽ではベートーベンなどが登場しています。因みに、教養は極めて国民国家的な概念なので、よく言われる「グローバルな教養」という概念は矛盾を含んでいることになります。
「一般教育」は一般大衆に向けて機能する基礎教育
「一般教育」(General Education)の出自は、20世紀初頭のアメリカです。アメリカのカレッジでは、一般大衆に向けて機能する基礎教育的な仕組みを必要としました。ここに登場したのが一般教育という考え方です。人類の未来的な知性を具えた市民の育成を目指しました。この概念は、自然科学、(Natural Science)、社会科学(Social Science)、人文科学(Humanities)の3分野を横断しようとします。日本では、この一般教育の考え方が、占領期にGHQの要請によってアメリカから派遣された米国教育使節団によってもたらされました。しかし、1991年の大綱化以降、大学の一般教育という区分は取り払われ、結果的に大学の広い意味での教養教育は急速に空洞化していきました。
文系と理系の袂をわけたのは19世紀の産業革命
――よく、理解できました。ところで、文系、理系という分け方はいつ頃から出てきたのですか。
吉見 そのエポックメイキングなできごとは産業革命です。19世紀以降、産業革命によって、世界中で、社会全般に機械技術、産業技術が行き渡っていきます。機械工学、土木工学などを中心に理系、自然科学的な知が社会に深く浸透していきました。その結果、社会全般の変化は理系主導で起こると考えられるようになり、人文社会科学系(文系)はそうした変化を批判するか、異なる価値を提示する立場に追いやられました。
つまり、「文系」と「理系」の区分は、近代産業社会以前には、明瞭ではなく、産業革命以降の科学技術と資本主義の結びついた体制において形成され、確立されてきたのです。文系の知が「役に立つ」という検証は済んでいる
そして、この時から、文系は、理系に対して何ができるかを考えるようになります。特にドイツの新カント派の学者によって研究が進められ、その中でも重要な人物は、ドイツの社会学者マックスウェーバーです。彼が注目したのが「価値」という概念です。彼は名著『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』(1904-1905年)の中で、「目的合理的行為」と「価値合理的行為」について言及、「目的合理性が自己完結したシステムは、いつか価値の内実を失って化石化していくのであるが、目的合理的な行為自体がその状態を内側から変えていくことはできない」という暗たんたる予言をしています。そして、ウェーバーはそのように空疎になったシステムを突破するのに、価値合理性やカリスマといった別の介入回路を考えようとしたわけです。
つまり、目的遂行型の有用性(手段的合理性)、目的に関して「役に立つこと」は、与えられた目的や価値がすでに確立されていて、その達成手段を考えるには有効ですが、そのシステムを内側から変えていくことはできません。従って、目的や価値の軸そのものが変化した時、一挙に役に立たなくなってしまうのです。
新自由主義という大きな流れに翻弄されている今
これまでのお話でお分かりにように、「文系は役に立つのか」の問に答えることを迫られたのは、21世紀初頭の私たちが最初ではありません。産業革命後の19世紀末からこの問いに多くの学者が取り組みました。そして、20世紀を通じ、理系とは別の意味で、「文系は役に立つ」ことを検証してきたのが、他ならぬ「人文社会科学」(文系)の歴史そのものなのです。このことを、多くの読者、国民の皆さんにご理解いただきたいと思っています。
私は混沌とした日本情勢、世界情勢の今、また「儲かるかどうか」ですべてが決まっていく新自由主義の大きな流れに翻弄されている今だからこそ、本当に必要なのは「文系の知」であることを確信しています。
――本日は、お忙しい中ありがとうございました。
(了)
【金木 亮憲】<プロフィール>
 吉見 俊哉(よしみ・しゅんや)
吉見 俊哉(よしみ・しゅんや)
1957年、東京都生まれ。東京大学大学院情報学環教授。同大学副学長、大学総合教育センター長などを歴任。社会学、都市論、メディア論、文化研究を主な専攻としつつ、日本におけるカルチュラル・スタディーズの中心的な役割を果たす。主な著書に『都市のドラマトゥルギー ―東京・盛り場の社会史』『「声」の資本主義―電話・ラジオ・蓄音機の社会史』、『大学とは何か』、『夢の原子力』、『「文系学部廃止」の衝撃』他多数。関連記事
2024年4月8日 14:102024年4月3日 15:002024年4月1日 17:002024年4月18日 10:452024年4月15日 17:202024年4月5日 17:402024年4月18日 10:45
最近の人気記事
まちかど風景
- 優良企業を集めた求人サイト
-
 Premium Search 求人を探す
Premium Search 求人を探す
- 業界注目!特集
-
 産廃処理最前線
産廃処理最前線
サステナブルな社会を目指す
- MAX WORLD監修
-
 パーム油やPKSの情報を発信
パーム油やPKSの情報を発信
パームエナジーニュース







 出自が一番古いのは、キリスト教世界を背景にしたリベラルアーツです。これはもともと、ヨーロッパ中世の12、13世紀に誕生した大学における自由7科(文法学、修辞学、論理学、代数学、幾何学、天文学、音楽)のことを言います。このリベラルアーツは、当時「有用な学」と言われた、神学(神の役に立つ)、法学(国家の役に立つ)、医学(人の役に立つ)と対比されていました。その構成は、文系・理系・芸術系で、3:3:1になっています。今回の一部の報道では、リベラルアーツ=文系と考えているような発言もありましたが、それは誤りです。リベラルアーツの半分は理系なのです。この自由7科はその後、哲学になっていきます。哲学者のデカルト(解析幾何学の原理を確立)やライプニッツ(微積分法を発見)が同時に数学者であったのはごく自然のことだったのです。
出自が一番古いのは、キリスト教世界を背景にしたリベラルアーツです。これはもともと、ヨーロッパ中世の12、13世紀に誕生した大学における自由7科(文法学、修辞学、論理学、代数学、幾何学、天文学、音楽)のことを言います。このリベラルアーツは、当時「有用な学」と言われた、神学(神の役に立つ)、法学(国家の役に立つ)、医学(人の役に立つ)と対比されていました。その構成は、文系・理系・芸術系で、3:3:1になっています。今回の一部の報道では、リベラルアーツ=文系と考えているような発言もありましたが、それは誤りです。リベラルアーツの半分は理系なのです。この自由7科はその後、哲学になっていきます。哲学者のデカルト(解析幾何学の原理を確立)やライプニッツ(微積分法を発見)が同時に数学者であったのはごく自然のことだったのです。 吉見 俊哉(よしみ・しゅんや)
吉見 俊哉(よしみ・しゅんや)