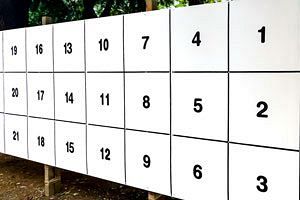【働き方改革はブラック企業を漂白できるか】「何を言うか」より「何をしたか」で評価される企業へ(中)
-

-
ブラック企業アナリスト 新田 龍 氏
経営者や上司が自らの立場を利用し、地位や人間関係で立場の弱い従業員や部下に対して精神的・身体的な苦痛を与えることが日常的に行われている会社―これらは俗に「ブラック企業」と呼ばれる。その一方で、あり得ない主張や批判を繰り返して職場に迷惑をかけ、業務のスムーズな進行を妨げる「ブラック社員(モンスター社員)」も問題視されるようになってきた。「ブラック企業アナリスト」として双方の事情に詳しい新田龍氏に、双方のブラックたる所以について聞いた。
【聞き手:長谷川 大輔】
なぜブラック企業が生まれるのか
(1)労働行政・司法の問題
戦後間もない時期に制定された労働法規の重点指導対象は「工場労働者の安全衛生」であり、法違反に対して罰則が緩く、違法行為の抑止力になっていません。
司法判断面においては、戦後復興期に国として財源が不足しているなかでも社会保障を拡充せねばならないという局面において、「企業が雇用を増やすことで社会保障の一部を担う」「企業が負担する雇用と保障について行政が支援する」「労働組合が経営を監視する」という役割分担ができました。
従って現在に至るまで、司法は「解雇」に対しては大変厳しい一方で、「長時間労働」「サービス残業強要」「残業代未払い」といったそれ以外の違反を大目に見ているところがあります。すべては当時の役割分担に起因していると思われます。
「長時間労働」「サービス残業強要」「残業代未払い」はれっきとした労基法違反ですが、いまだに多くの違反が発生しているのは「違反しても企業にとっては大きな痛手にならないため」でしょう。
実際、労基法違反はめったに取り締まられることはなく、労働基準監督署(以下、労基署)から臨検を受けて違法行為が見つかっても、是正勧告がなされて書面を提出すれば終わりです。労基署からの勧告を複数回無視するとようやく書類送検されますが、そこから起訴されることは稀です。仮に起訴され、有罪判決を受けても、それに対する罰則の多くが「6カ月未満の懲役もしくは30万円以下の罰金」であり、法律とその運用がまったく抑止力になっていません。そればかりか、「有罪でもそれくらいの罰で済むなら…」と、かえって違法行為を助長している節があります。
労基署も人員不足により、対応が行き届いていないことも背景にあります。日本は労働者数あたりの労働基準監督官(以下、監督官)の数が他国と比較して相対的に少なく、監督官が日本に存在するすべての事業所を訪問するとなると、現在の監督官の人数では何十年もかかってしまう計算になります。こうした状況から、労基署に持ち込まれる相談案件の数が多すぎて、実質的には捌ききれていない状態が続いています。人員増の要求は以前から行われていますが、厳しい財政状況もあり、なかなか難しいようです。
(2)雇用慣行の問題
日本の雇用システムは国際的にみて独特の形態を採っています。専門用語で説明すると、国際的には「ジョブ型雇用」「職務給」、日本は「メンバーシップ型雇用」「職能給」と分類されます。
日本以外のほぼすべての国では、仕事に対して求められる資質や経験が決まっており、資質をもった人がその仕事に応募して働く―いわば「仕事に人が就く」形態であり、報酬も仕事に応じて決まるので「職務給」と呼ばれています。具体的な職務に対応するかたちで労働者と雇用契約を結ぶため、その職務に人員が必要になれば都度採用し、必要なくなったり、採用した人が契約に応じた働きができなくなったりすれば、企業は整理解雇をすることができます。海外で「簡単に会社をクビになる」といわれるのはそのためです。
一方で日本の「新卒一括採用システム」は、会社組織に対して求める人物像が決まっており、「意欲」「主体性」「粘り強さ」といった資質をもった人がその会社に応募して採用されます。仕事は入社後、人に合わせて決まるかたちをとるので、「人に仕事が就く」形態であり、報酬は業務処理力(通常は年齢=年功)に応じて決まるため、「職能給」と呼ばれます。
日本の場合、「メンバーシップ」の名の通り、入社したらその組織のファミリーの一員のごとく扱われます。ファミリーであるから大切に扱われ、多少仕事ができなくてもいきなり会社をクビになることは基本的になく、異動や転勤、転籍、出向などで組織内に温存されることになります。人や状況に合わせて仕事が変わっていくことが前提の仕組みであるため、組織としては長年同じ仕事をやらせてスキルが固定化するよりは、数年に一度のペースで配置転換することで、さまざまな状況に対応できる従業員を育てようとするわけです。そうなると、会社をクビにはなりにくい代わりに、労働者は企業内のすべての業務に従事する「義務」が発生します。
会社側が一方的に転勤や転籍、出向などを命じることは、日本以外の諸外国ならパワハラ扱いになるくらいの事態なのですが、日本の場合は当然のこととして認識されています。実際これまで、会社の残業命令や転勤辞令を拒否したことを理由に、社員を解雇した事件が裁判で争われたことがありましたが、最高裁で「合法」という判断がなされています。諸外国では不当解雇扱いになることから、世界的に見れば日本が特殊であるという事情がみてとれます。
とはいえ、会社側にそこまでの権限を認めているのも、「あくまで会社が従業員をファミリーの一員として大切に扱い、たとえ業績が悪くても安易にクビにせず雇用し続ける」という前提があっての話です。その前提条件を守らずに、従業員を酷使するだけのアンフェアな会社は、ブラック企業以外の何者でもありません。
(3)ユーザーや外野の問題
これは日本社会の「空気感」のようなものと密接に関係しています。長らく儒教的文化の影響を受けたことが一因かもしれませんが、日本では「立場が下の人は、上の人のいうことを黙って受け入れる」といったような無言の社会的圧力があり、それに対して異論を唱えることは「和を乱す行為」と捉えられてしまいます。教育やスポーツ指導の現場でいまだに体罰やパワハラがニュースになり、職場では相変わらずセクハラやモラハラが横行しているのも、同じ構造でしょう。この体質が、ブラック企業が生まれる根底にあります。
過剰労働(ブラック労働)とのつながりでいえば、その背景にはサービスや商品に完璧を求め、無限に要求をエスカレートさせる「モンスター客」や「クレーマー」などの存在があります。
彼(彼女)らは、「お金を出しているのだから」「お客さまは神さまだから」という意識が根強く、初めから自分たちの立場を上と見なしています。「お客さまは神さま」というフレーズは、演歌歌手の三波春夫が発したことで有名になった言葉ですが、「お客さまを神さまと捉える。そうすることで芸に磨きをかけ、心の雑念を払い最高の芸を見せることができる」というのが本来の主旨であり、決して「お金を払った客なんだから、神さま扱いしろ」という意味ではありません。従って、相応の対価も払わず、サービス水準の要求ばかり厳しい客は「神さま」ではありません。
高いレベルのサービスを受けて気持ちよくなりたいのであれば、それに見合った金額を支払うべきですが、こうした誤った認識が過剰な水準の接客サービスを従業員に強いることにつながり、結果として、対抗手段をもたない末端の従業員の過剰労働につながっています。
(4)就職希望者と従業員の問題
求人への応募は誰でもできますが、昨今は書類選考や面接の基準も厳しくなっています。どんな業界、どんな会社でも必ず尋ねられるのは、「あなたがこれまでに力を入れて取り組んだことは何ですか?」という質問です。就職面接に至るまでの人生において、「目標をもって主体的に取り組んだか」「困難があってもめげずにやり抜いたか」さらには「経験から何を学び、どんな強みを普遍的に発揮できているか」が問われます。それを継続するのは大変ですが、大変な思いをした人はやはり、優良企業(ホワイト企業)に受かっています。
ブラック企業の場合、「採用時においては頭数さえそろえば誰でもいい」「入社後は仕事についてこられない者は辞めればいい」と思っています。そんな会社に限って、「書類選考はありません!」「100%面接します!」と甘い声をかけます。そして面接を受けてみると、わずか10分程度の雑談であっさり「内定です!ぜひあなたと一緒に働きたい!」などと言います。新卒採用者のみならず中途採用者にもいえることですが、希望していた企業に落ちて「自分の価値なんてないのかも…」と心が弱くなっている者にとって、この言葉は心地よいものといえるでしょう。しかしこれが、「ろくに考えず、ブラック企業に入ってしまう瞬間」です。
(つづく)
<プロフィール>
 新田 龍(にった・りょう)
新田 龍(にった・りょう)
1976年生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業後、複数の上場企業において事業企画、営業管理職、コンサルタント、人事採用担当職などを歴任。2007年「働き方改革総合研究所(株)」設立。働き方改革推進による労働環境とレピュテーション改善、およびブラック企業やブラック社員など、悪意ある取引先や従業員に起因するトラブル解決を手がける。また、厚生労働省プロジェクト推進委員として政策提言を行うとともに、各種メディアで労働問題、ブラック企業問題に関するコメンテーターとしても活動。「ワタミの失敗」(KADOKAWA)ほか著書多数。関連記事
2024年4月8日 14:102024年4月3日 15:002024年4月1日 17:002024年4月18日 10:452024年4月15日 17:202024年4月5日 17:402024年4月18日 10:45
最近の人気記事
まちかど風景
- 優良企業を集めた求人サイト
-
 Premium Search 求人を探す
Premium Search 求人を探す
- 業界注目!特集
-
 産廃処理最前線
産廃処理最前線
サステナブルな社会を目指す
- MAX WORLD監修
-
 パーム油やPKSの情報を発信
パーム油やPKSの情報を発信
パームエナジーニュース








 新田 龍(にった・りょう)
新田 龍(にった・りょう)