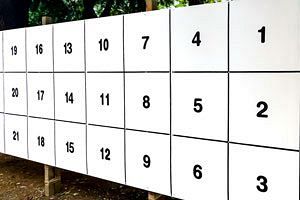【凡学一生のやさしい法律学】他山の石~香港の警官起訴の騒乱で、香港政府が権利濫用
-

-
香港政府の権利濫用と違法裁判
香港で騒乱が起きた。警察官の違法発砲により傷害を受けた市民が私人による刑事起訴を行ったところ、香港政府が公訴棄却を求め、裁判所が公訴棄却を認めたという事件である。香港は旧宗主国である英国の刑事司法制度を採用しており、私人にも刑事起訴権が認められている。
日本やアメリカ、フランス、ドイツでは刑事起訴権(公訴権)は「国家独占主義」である。検察官の公訴権の濫用に苦しむ日本にとって、香港で起こった事件はまさに「他山の石(※)」となる事例である。
どのような制度であっても、その制度を運用する人間が「腐敗」していれば、結果として政治の腐敗が起こる。公訴棄却をした裁判官がもちろん「腐敗役人」であるが、火事の対岸にいる日本国民は、腐敗の原因や、法論理的には腐敗論で誤った議論とは何であるかについての実態を知らねばならない。まったく同じ論法が日本でも濫用されているからである。
これは裁判法の基本問題であり、濫用論のルーツでもある。国民が真に司法権を自身のものとするために、最低限理解しておきたいことであり、一方で法匪によるもっとも初歩的な権利濫用手段でもある。
合理的に見える制度が両刃の剣に
 裁判の基本手続に「要件審理」という手続があることはあまり知られていない。要件審理とは、民事・刑事裁判を問わず、すべての公的裁判・審判行為の基本的手続であり、裁判が可能な事案であるかという形式的審査である。裁判にこのような前工程としての手続が存在するのには、極めて合理的な理由がある。その制度の合理性が明白に理解できるように、具体的事例を挙げて説明する。
裁判の基本手続に「要件審理」という手続があることはあまり知られていない。要件審理とは、民事・刑事裁判を問わず、すべての公的裁判・審判行為の基本的手続であり、裁判が可能な事案であるかという形式的審査である。裁判にこのような前工程としての手続が存在するのには、極めて合理的な理由がある。その制度の合理性が明白に理解できるように、具体的事例を挙げて説明する。たとえば、明智光秀の子孫が、「光秀が謀反人である」との史実を記載した歴史学者を、先祖の名誉、さらに明智一族の名誉を毀損する行為として民事刑事裁判を提起した場合、裁判所は「法的紛争」として受理できるか、という問題である。
このような歴史的事実、宗教的事実、学術上の争いについては「法律上の争訟ではない」として「本案審理」に入る前に裁判手続が否定され、刑事では「公訴棄却」、民事では「却下」判決となる。
一見するとこの制度は合理的に見えるが、実際には濫用されており、本来ならば本案審理して事実について黒白をつけるという裁判所の義務を放棄した違法裁判例が、極めて多数存在する。
香港の事例も、事案を審理して有罪無罪を判決すべき事例であって、香港政府が公訴棄却(裁判拒否)を主張することそのものが権利濫用である。さらに香港政府がもつ公訴棄却請求権の濫用を認めた裁判所も、「権利濫用を認めた」という意味で違法裁判である。
そこで被害を受けた市民は、不法行為を理由として民事裁判による被害の救済を求めることとなる。裁判官の異なる民事裁判で請求が認められれば、刑事裁判官の違法行為は同じ法律家仲間の民事裁判官からも批判を受けたことになる。
伊藤詩織事件での司法権の運用
似たような司法権の運用が日本でも最近報道された。伊藤詩織女史が被害を受けた性的暴行事件(以下、伊藤詩織事件)である。日本の公訴権は検察官に独占されているが、警察にも刑事事件捜査権があり、公訴提起を請求する権利・義務がある。
伊藤詩織事件では、警察の捜査権行使の段階で「違法行為がある」とされた。検察官の公訴提起を求める市民の告訴告発権とそれに対する検察官の不起訴処分については、検察審査会への請求が制度上は整備されている。しかし、冒頭に述べたように、それを運用する人間が「腐敗」していれば、いかなる制度も正しく機能しない。
市民にとって納得できない権力的判断がある時は、往々にして市民に隠された権力の腐敗構造が存在している。日本の国民にとって、検察審査会制度は完全に闇のなかに埋没しているといえる。
検察審査会制度では、裁判所が任命する弁護士のみが就任できる補助審査員が、無作為抽出された法律の素人である市民審査員を(裁判所と検察の意向を忖度して)自由自在に誘導していることは、一部の弁護士や裁判官、裁判所関係者のみが知る事実だ。
もちろん誘導された市民審査員のなかには、補助審査員である弁護士の誘導に違和感を持った人がいるだろうが、絶対的な守秘義務を課された立場に置かれるため、不当な経験を公に表明することができず、無言を貫き通すしかないだろう。
無垢の市民が官憲の権利濫用の「ダシ」にされているのが日本の刑事司法の実態である。
※他山の石
中国最古の詩集「詩経」にある故事に由来する言葉。「よその山から出た粗悪な石も自分の宝石を磨くのに利用できる」ことから「他人のつまらぬ言行も自分の人格を育てる助けとなる」という意味(文化庁月報・2011年10月号・No.517)。^関連記事
2024年4月8日 14:102024年4月3日 15:002024年4月1日 17:002024年4月18日 10:452024年4月15日 17:202024年4月5日 17:402024年4月18日 10:45
最近の人気記事
まちかど風景
- 優良企業を集めた求人サイト
-
 Premium Search 求人を探す
Premium Search 求人を探す
- 業界注目!特集
-
 産廃処理最前線
産廃処理最前線
サステナブルな社会を目指す
- MAX WORLD監修
-
 パーム油やPKSの情報を発信
パーム油やPKSの情報を発信
パームエナジーニュース







 裁判の基本手続に「要件審理」という手続があることはあまり知られていない。要件審理とは、民事・刑事裁判を問わず、すべての公的裁判・審判行為の基本的手続であり、裁判が可能な事案であるかという形式的審査である。裁判にこのような前工程としての手続が存在するのには、極めて合理的な理由がある。その制度の合理性が明白に理解できるように、具体的事例を挙げて説明する。
裁判の基本手続に「要件審理」という手続があることはあまり知られていない。要件審理とは、民事・刑事裁判を問わず、すべての公的裁判・審判行為の基本的手続であり、裁判が可能な事案であるかという形式的審査である。裁判にこのような前工程としての手続が存在するのには、極めて合理的な理由がある。その制度の合理性が明白に理解できるように、具体的事例を挙げて説明する。