
<山口銀行前身、第百十銀行の沿革(30)~銀行法の制定と県内銀行の合併(4)>
前節は藤田銀行の設立会社で山口県と関係が深かった藤田組とその系列会社の歴史に話がそれてしまいましたが、本題に戻すことにします。
2―県下の銀行合同の動きと挫折
銀行法が公布された昭和2年(1927)当時、山口県下にはまだ12行が存立しており、政府は大蔵省検査官を県に派遣し、県知事を通じて、県下銀行の合同促進についての各行の意見を聴取することとし、同年10月28日県庁に各行代表を召集した。ここに大島銀行常務中司四郎・取締役矢田部三四 ~以下略~ の10行11名が集まった。本会合で大森吉五郎知事および河西金城大蔵省検査官は、銀行合同の必要性を訴え県下の銀行合同のより一層の推進を強く要請した。
出席していない周防銀行は休業中で解散待ちの状態、周東産業銀行は華浦銀行との合併手続き中であった。参加行の中でも、鹿野銀行はこの四月休業し、一人立ちは困難な状態にあり、個人経営の萩野銀行も解散予定であった。また、萩銀行および防長銀行の2行は藤田銀行の傘下にあり、早晩これに合併するものとみられていた。そこで最も問題となったのは、合併の格となることが予定されている百十銀行を除く5行(大島・船城・宇部・長周および華浦)の思惑、考え方であった。
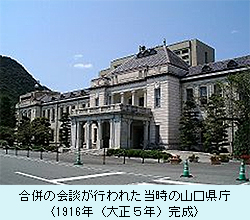 会合のあった1927年(昭和2年)10月28日時点では、山口県下には12行あったが周防銀行、鹿野銀行、周東銀行、萩野銀行の4行が解散・廃業または合併により消滅。残り8行のうち、藤田銀行傘下の萩銀行と防長銀行の2行は藤田銀行に吸収合併されることになっており、山口県下は6行体制になると見られていた。しかし翌年の1928年(昭和3年)藤田組の経営難から経営破綻に追い込まれた藤田銀行は、萩銀行と防長銀行を吸収合併することなく、同年11月、百十銀行に2行を譲渡しており、結果的に山口県内は6行体制となった。残った6行についても合併を進めたい大蔵省に対して、各行それぞれの思惑や考え方の相違により合併は一時頓挫することになる。
会合のあった1927年(昭和2年)10月28日時点では、山口県下には12行あったが周防銀行、鹿野銀行、周東銀行、萩野銀行の4行が解散・廃業または合併により消滅。残り8行のうち、藤田銀行傘下の萩銀行と防長銀行の2行は藤田銀行に吸収合併されることになっており、山口県下は6行体制になると見られていた。しかし翌年の1928年(昭和3年)藤田組の経営難から経営破綻に追い込まれた藤田銀行は、萩銀行と防長銀行を吸収合併することなく、同年11月、百十銀行に2行を譲渡しており、結果的に山口県内は6行体制となった。残った6行についても合併を進めたい大蔵省に対して、各行それぞれの思惑や考え方の相違により合併は一時頓挫することになる。
*記事へのご意見はこちら
※記事へのご意見はこちら
