
<山口銀行前身、第百十銀行の沿革(36)~山口銀行創立までの経緯(1)>
1―山口県下銀行合同の動き
山口県内に本店を構える銀行は、昭和3年(1928)11月に百十銀行が防長銀行および萩銀行を合併し、同4年に個人銀行の萩野銀行が廃業して以来、百十、船城、宇部、華浦、長周および大島銀行の6行体制が、日中事変に入っても続いていた。
県下の銀行合同の動きは、大島銀行の『重役会議事録』によると「最近トナリ居ル華浦、宇部、船城、大島ヲ合併シテ新立銀行設立ノ問題ニ当行トシテ如何ナル處置ニ出ツルカヲ審議ス約二時間半決議ヲ見ズシテ次会ニ譲ル(昭和15.10.21開催)とあり、文意から昭和15年の秋には各行ともこの問題について検討していたことがうかがえる。しかし、その後の大島銀行の重役会で本件が議題となったこともなく、また、その他各行の資料にも見当たらないので、ほどなく立消えとなったものであろう。なお、この議事録からも分かるようにこれには百十と長周銀行の名前が見えないことから、当時、山口県では2行体制が企図されていたのかもしれない。
次に表面化したのは昭和17年で、大島銀行は同年3月10日付大蔵省銀行局長の頭取宛召集を16日に受け取り、17日その準備のため中司馨輔取締役が日本銀行広島支店へ出張して情報を収集し、同月23日の重役会議で詳細に報告、併せて頭取の上京を同月28日午前10時と決めている。これについて県下他行の資料はないが、大蔵省は同様に呼び出したと思われ、これが山口銀行合併新立の具体的な動きの最初である。
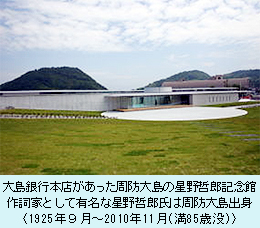 銀行法が公布された昭和2年(1927)当時、山口県下にはまだ普通銀行12行が存立していたが、銀行法の施行を契機に、その内6行が合併や廃業などにより消滅し、山口県内の銀行は6行となった。大蔵省の一県一行主義の構想は成功するかに見えたが、昭和2年10月に華浦銀行の取締役会がその覚書を否決したため頓挫している。その約15年後にやっと合併が具体化することになる。大島銀行の『重役会議事録』には太平洋戦争が始まるにつれて、一県一行主義により銀行合併を推し進める大蔵省の意向に従わざるを得ない状況になっていくことが読み取れる。
銀行法が公布された昭和2年(1927)当時、山口県下にはまだ普通銀行12行が存立していたが、銀行法の施行を契機に、その内6行が合併や廃業などにより消滅し、山口県内の銀行は6行となった。大蔵省の一県一行主義の構想は成功するかに見えたが、昭和2年10月に華浦銀行の取締役会がその覚書を否決したため頓挫している。その約15年後にやっと合併が具体化することになる。大島銀行の『重役会議事録』には太平洋戦争が始まるにつれて、一県一行主義により銀行合併を推し進める大蔵省の意向に従わざるを得ない状況になっていくことが読み取れる。
※記事へのご意見はこちら
