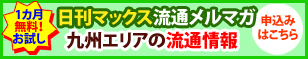特 集
「自爆民主党解散」シリーズ
日本国家"根源的変革"の処方箋シリーズ
高島市長へ愛の告知
脱原発・新エネルギー
守旧派拠点・薩摩
福岡の特選企業
士業事務所 戦略シリーズ
東日本大震災
倒産を追う
直撃インタビュー
東京レポート
自立する地域社会
追跡!裁判事件簿
検証ベスト電器
糸島ローカルビジョン
動画チャンネル
特別取材
経済小説
クローズアップ
輝く九州の女性たち
コラム・寄稿
コダマの核心
「人生」極める
SNSI中田安彦レポート
深層WATCH
清明がほえる
濱口和久「本気の安保論」
チャイナビジネス最前線
となりの新華僑・華人の知恵
上海最先端レポート
中洲バトルロワイヤル
竹原信一氏・特別寄稿
未来トレンド分析シリーズ
流通大競争時代
大手食品営業マンの告白
覆面ヘッドハンターの一刀両断!
地域づくりにマーケティング発想を
福岡への提言
読者投稿・ご意見メール
書評・レビュー
連載コラム
最新情報
耳より情報
企業
経済
流通
建設
住宅・不動産
健康・医療
最新金融情報
政治
行政
社会
発信!北九州
信用調査レポート
倒産情報(九州・山口)
倒産情報(全国)
イベント情報
セミナー情報
新商品・新技術
発信!北九州
<山口銀行の誕生~頭取交代の変遷(1)>
1944(昭和19)年3月31日、百十銀行を存続銀行として、華浦銀行、宇部銀行、船城銀行、および大島銀行の5行合併により、山口銀行が誕生した。
合併により新設された山口銀行の初代頭取には三和銀行出身の広津次郎氏が就任。その5年後の1949(昭和24)年5月に、同じ三和銀行出身で常務取締役の布浦眞作氏が頭取に就任した。
山口銀行創立30周年を節目として、1974(昭和49)年5月10日に、25年間頭取であった布浦氏が取締役会長に、筆頭の専務取締役であった伊村光氏が頭取に就任。プロパーの頭取誕生であった。
新頭取に就任した伊村光氏の略歴は下記の通り。
1935(昭和10)年3月 山口高等商業学校(現山口大学)卒業後、百十銀行入行
1944(昭和19)年3月 合併した山口銀行に入行
1960(昭和35)年4月 頭取室長、調査部長、東京支店長を経て取締役に就任
1970(昭和45)年4月 常務取締役を経て専務取締役に就任
1974(昭和49)年5月 頭取に就任
1992(平成4)年6月 取締役会長に就任
 伊村頭取体制が発足した5年後の79年(昭和54年)10月に、徳山東支店支店長による定期預証書偽造事件が発覚。取引先の不動産業者の倒産を回避するために、77年から79年にかけて、金融業者の導入預金を不正に受け入れる手口であった。この事件による実質の損害額は16億9,000万円に上ったと言われ、現役の支店長による不祥事件は銀行業界全体の信用著しく傷付けることとなった。そのため布浦眞作代表取締役会長が代表権を返上するとともに取締役相談役へ、また出口一視筆頭専務もその責任を取って辞任している。当時の徳山地区の支店を統括する母店長は、田中耕三取締役徳山支店長であった。その後約5年以上山口銀行は新規支店の出店が認められず、店舗展開において大きな後れを取ることになった。
伊村頭取体制が発足した5年後の79年(昭和54年)10月に、徳山東支店支店長による定期預証書偽造事件が発覚。取引先の不動産業者の倒産を回避するために、77年から79年にかけて、金融業者の導入預金を不正に受け入れる手口であった。この事件による実質の損害額は16億9,000万円に上ったと言われ、現役の支店長による不祥事件は銀行業界全体の信用著しく傷付けることとなった。そのため布浦眞作代表取締役会長が代表権を返上するとともに取締役相談役へ、また出口一視筆頭専務もその責任を取って辞任している。当時の徳山地区の支店を統括する母店長は、田中耕三取締役徳山支店長であった。その後約5年以上山口銀行は新規支店の出店が認められず、店舗展開において大きな後れを取ることになった。
徳山東支店事件の6年前の73年10月21日に、滋賀銀行山科支店の奥村彰子(当時42歳)が、銀行史上空前の9億円横領の容疑で逮捕されたが、徳山東支店事件はそれを上回る金額であった。その後91年(平成3年)8月13日、東洋信用金庫(大阪市)を舞台に、興銀などを巻き込んだ尾上縫による3,240億円(預金残高を上回る)架空預金証書事件が発生。平成バブル崩壊を象徴する大スキャンダルが導火線となって、大手金融機関は再編への道を辿ることになる。
*記事へのご意見はこちら