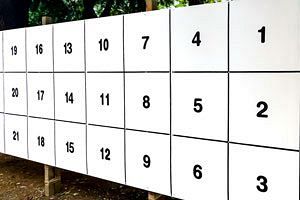認知症徘徊時の事故の責任と差別意識(前)
-

-
大さんのシニアリポート第43回
徘徊中に列車にはねられた認知症の男性(当時91歳)の遺族が、JR東海に損害賠償を求められていた裁判、最高裁で無罪の判決が下された。遺族がもっとも納得したのが、木内道祥裁判官の「認知症の人が行動を制限されないことも重要だ」(「朝日新聞」3月22日)という発言だったという。しかし、このことが逆に「監督責任」という問題を再提起することにもなった。認知症の患者を持つ家族が抱えている悩み、周辺(家族、親戚、友人たち)の無理解と差別意識を含め現状を報告したい。
 わたしが住む地域の近くに、65歳以上の住民が50パーセントを超す「限界団地」(冠婚葬祭など、社会的共同生活の維持が困難な地域)がある。自治会長は「毎週葬儀があって大変」と、幾分自嘲気味に話す。当然認知症の人も急増している。ある日、ひとりの高齢者が忽然と姿を消した。家族や自治会の役員、住民、警察官などが手分けして付近を捜した。市の広報に連絡して有線放送を使い、市民に協力を求めたものの、ようとして消息がつかめない。彼女は数年前に夫を亡くし、その頃から認知症の症状を示すようになったという。役員のひとりがあることを思い出し、「旦那さんと行った思い出の場所」を家族に訪ねた。「河口湖です」と答えた。早速関係部署に連絡を入れてみると、これがドンピシャリ。管理事務所に保護されていたという。しかし、捜索に参加してくれた住民から、「家族の無責任」という非難の声が漏れ聞こえた。今でもその家族と住民との間はしっくり来ないと自治会長は話す。
わたしが住む地域の近くに、65歳以上の住民が50パーセントを超す「限界団地」(冠婚葬祭など、社会的共同生活の維持が困難な地域)がある。自治会長は「毎週葬儀があって大変」と、幾分自嘲気味に話す。当然認知症の人も急増している。ある日、ひとりの高齢者が忽然と姿を消した。家族や自治会の役員、住民、警察官などが手分けして付近を捜した。市の広報に連絡して有線放送を使い、市民に協力を求めたものの、ようとして消息がつかめない。彼女は数年前に夫を亡くし、その頃から認知症の症状を示すようになったという。役員のひとりがあることを思い出し、「旦那さんと行った思い出の場所」を家族に訪ねた。「河口湖です」と答えた。早速関係部署に連絡を入れてみると、これがドンピシャリ。管理事務所に保護されていたという。しかし、捜索に参加してくれた住民から、「家族の無責任」という非難の声が漏れ聞こえた。今でもその家族と住民との間はしっくり来ないと自治会長は話す。以前、知人の兄の妻が若年性認知症になり、三女が献身的に自宅で世話をしたものの、「認知症が家族にいることは恥。世間体が悪い。親戚の目も気になる」という夫の考えから、一方的に施設に強制的に入所。その後、三女と対立を生んだという報告をしたことがある。かつて「惚(呆)け」と呼ばれ、蔑まされた「認知症」という症状に関して、無関心、無理解、差別意識がこん日でも働いている気がしてならない。余談だが、「惚け」は“惚れる”と同じ字体だ。「夢中になると、相手の素顔が見えなくなる」という意味が込められていることを思いだして欲しい。
今回、無罪の判決を勝ち取った遺族も、当初、JR東海という大企業と戦うことに、家族や親戚から「肩身が狭い」「うわさになる」と反対されたという。“裁判”という非日常的な忌避感以外に、「認知症の徘徊時に起こした事故で裁判するというのはみっともない、見苦しい」という考えが込められていたのではないか。一審では男性の妻と長男に720万円、二審では男性の妻(92歳)のみに360万円の賠償を命じられたとき、長男は「もうやめようかと迷った」と語っている。「認知症」という言葉に背負わされた忌まわしい背後霊が動く。それを喝破したのは、「ひとごととは思えない」「在宅介護を続けている人たちのために頑張って」(長男)という手紙やメールだった。
遺族の長男は、「一、二審では『認知症の人が社会に面倒を起こさないようにどう監督するか』という点が強調され、認知症の人自身の生き方に寄り添う視点がないと感じていた」と述べている。認知症の人は、過去の人生を含め、人間としての尊厳すべてが失われたわけではない。かつて、認知症(当時は惚け)で昼夜逆転した父親の面倒を看ていたわたしは、演劇評論家として坪内逍遙先生に仕えた父の演劇人としての矜持に触れたことが数知れずあった。ある夜、ベッドに寝ていた父に、「ここはどこだ。君は誰だ」と聞かれたことがあった。咄嗟に、「先生、ここは夜行列車の寝台車です。先乗りで名古屋に向かっています。明朝着きますから、ゆっくりお休みください。わたしは劇団員の研究生で、先生の付き人をやらせていただいております」といった。野分めいた風が窓外の木々を揺らせていたのが、丁度列車が進行しているような風景に見えた。父は数え90歳になる直前に逝った。わたしはそういう父を看たことに満足している。
 遺族の長男も、「面倒を恐れて何かを奪うのではなく、なるべくおやじらしく過ごさせてやりたかった」と述べている。その結果が“鉄道事故”を起こした。裁判では、「責任能力のない人が起こした行為に賠償責任を負うと定めた民法上の『監督義務者』に、介護する家族が当たるかどうかが争点となった」(長男)。裁判官五人全員が「当たらない。監督義務者に準ずる立場」とした。「介護を頑張るほど、自分から『監督義務』に近づいてしまう。でも、ちゃんと実情を見て義務を果たしたと考え、免責してくれたので納得がいく」と長男は語る。
遺族の長男も、「面倒を恐れて何かを奪うのではなく、なるべくおやじらしく過ごさせてやりたかった」と述べている。その結果が“鉄道事故”を起こした。裁判では、「責任能力のない人が起こした行為に賠償責任を負うと定めた民法上の『監督義務者』に、介護する家族が当たるかどうかが争点となった」(長男)。裁判官五人全員が「当たらない。監督義務者に準ずる立場」とした。「介護を頑張るほど、自分から『監督義務』に近づいてしまう。でも、ちゃんと実情を見て義務を果たしたと考え、免責してくれたので納得がいく」と長男は語る。今回、最高裁で無罪の判決が出たとはいえ、「どんな場合に責任を負うのか」については結論が出ていない。「家族の身体の状態や介護実態などによっては、責任が生じる場合がある」(同)とも述べている。今回は、長男が遠方に別居、妻(当時85歳)は、介護が必要とされる状態だった。だから免責となった。では、健康に問題がない家族などが介護していた状態で、様々な‘事故’を引き起こしたときは責任が生ずるということになる。「あるベテラン裁判官は『介護に積極的に関与すれば、賠償責任を負うリスクが高まる場合がある』」(同)という。そうでなくとも、親の介護をしたがらない家族が増えている。親身になって看れば看るほど賠償責任が増すというのでは、ますます関わりたがらない家族が増えるだろう。
(つづく)
<プロフィール>
 大山眞人(おおやま まひと)
大山眞人(おおやま まひと)
1944年山形市生まれ。早大卒。出版社勤務ののち、ノンフィクション作家。主な著作に、『S病院老人病棟の仲間たち』『取締役宝くじ部長』(文藝春秋)『老いてこそ二人で生きたい』『夢のある「終の棲家」を作りたい』(大和書房)『退学者ゼロ高校 須郷昌徳の「これが教育たい!」』(河出書房新社)『克って勝つー田村亮子を育てた男』(自由現代社)『取締役総務部長 奈良坂龍平』(讀賣新聞社)『悪徳商法』(文春新書)『団地が死んでいく』(平凡社新書)『騙されたがる人たち』(近著・講談社)など。関連キーワード
関連記事
2024年4月8日 14:102024年4月3日 15:002024年4月1日 17:002024年4月18日 10:452024年4月15日 17:202024年4月5日 17:402024年4月18日 10:45
最近の人気記事
まちかど風景
- 優良企業を集めた求人サイト
-
 Premium Search 求人を探す
Premium Search 求人を探す
- 業界注目!特集
-
 産廃処理最前線
産廃処理最前線
サステナブルな社会を目指す
- MAX WORLD監修
-
 パーム油やPKSの情報を発信
パーム油やPKSの情報を発信
パームエナジーニュース







 わたしが住む地域の近くに、65歳以上の住民が50パーセントを超す「限界団地」(冠婚葬祭など、社会的共同生活の維持が困難な地域)がある。自治会長は「毎週葬儀があって大変」と、幾分自嘲気味に話す。当然認知症の人も急増している。ある日、ひとりの高齢者が忽然と姿を消した。家族や自治会の役員、住民、警察官などが手分けして付近を捜した。市の広報に連絡して有線放送を使い、市民に協力を求めたものの、ようとして消息がつかめない。彼女は数年前に夫を亡くし、その頃から認知症の症状を示すようになったという。役員のひとりがあることを思い出し、「旦那さんと行った思い出の場所」を家族に訪ねた。「河口湖です」と答えた。早速関係部署に連絡を入れてみると、これがドンピシャリ。管理事務所に保護されていたという。しかし、捜索に参加してくれた住民から、「家族の無責任」という非難の声が漏れ聞こえた。今でもその家族と住民との間はしっくり来ないと自治会長は話す。
わたしが住む地域の近くに、65歳以上の住民が50パーセントを超す「限界団地」(冠婚葬祭など、社会的共同生活の維持が困難な地域)がある。自治会長は「毎週葬儀があって大変」と、幾分自嘲気味に話す。当然認知症の人も急増している。ある日、ひとりの高齢者が忽然と姿を消した。家族や自治会の役員、住民、警察官などが手分けして付近を捜した。市の広報に連絡して有線放送を使い、市民に協力を求めたものの、ようとして消息がつかめない。彼女は数年前に夫を亡くし、その頃から認知症の症状を示すようになったという。役員のひとりがあることを思い出し、「旦那さんと行った思い出の場所」を家族に訪ねた。「河口湖です」と答えた。早速関係部署に連絡を入れてみると、これがドンピシャリ。管理事務所に保護されていたという。しかし、捜索に参加してくれた住民から、「家族の無責任」という非難の声が漏れ聞こえた。今でもその家族と住民との間はしっくり来ないと自治会長は話す。 遺族の長男も、「面倒を恐れて何かを奪うのではなく、なるべくおやじらしく過ごさせてやりたかった」と述べている。その結果が“鉄道事故”を起こした。裁判では、「責任能力のない人が起こした行為に賠償責任を負うと定めた民法上の『監督義務者』に、介護する家族が当たるかどうかが争点となった」(長男)。裁判官五人全員が「当たらない。監督義務者に準ずる立場」とした。「介護を頑張るほど、自分から『監督義務』に近づいてしまう。でも、ちゃんと実情を見て義務を果たしたと考え、免責してくれたので納得がいく」と長男は語る。
遺族の長男も、「面倒を恐れて何かを奪うのではなく、なるべくおやじらしく過ごさせてやりたかった」と述べている。その結果が“鉄道事故”を起こした。裁判では、「責任能力のない人が起こした行為に賠償責任を負うと定めた民法上の『監督義務者』に、介護する家族が当たるかどうかが争点となった」(長男)。裁判官五人全員が「当たらない。監督義務者に準ずる立場」とした。「介護を頑張るほど、自分から『監督義務』に近づいてしまう。でも、ちゃんと実情を見て義務を果たしたと考え、免責してくれたので納得がいく」と長男は語る。 大山眞人(おおやま まひと)
大山眞人(おおやま まひと)