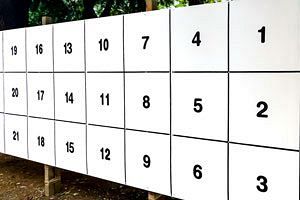問われた殺意、不条理な世界に「国民の常識」の限界(後)~知佐被告人判決
-

-
なぜ「未必的殺意」を認めなかったか
動機は大切だが、「殺してやる」とか「死んでしまえ」と思って、人を死なせたら、それは「確定的殺意」である。また、殺人罪でいうところの「殺意」は、そのような「意欲」や「動機」のことではない。「死んでもいい」と思って、あるいは「死ぬかもしれない」と認識して、「人が死ぬ危険性が高い行為」だと分かったうえで、その行為を行えば、「未必的殺意」になる。
たとえば、福岡市・天神で群衆に向けて銃を乱射して人が死亡すれば、本人が「殺す気はなかった」「人が死ぬとは思いませんでした」と殺意を否認しても、通常、殺人罪が成立すると考えるだろう。弾が当たった人が死なずにケガで済むことや誰にも弾が当たらないこともあるかもしれないが、常識に照らせば「死ぬ危険性の高い行為」だと分かって銃を撃ったと言えるのであって、責任能力を別にすれば、死亡させたいという意欲がなければ殺人罪が成立しないとか、なぜ天神で銃を乱射しようと思ったか動機が解明されないと殺人罪に問えないわけではない。「同じことをやれば死ぬと分かっていた」
 一般的には、なぜ死んだかが特定できないのに、「死ぬ危険性の高い行為」を行ったのかどうかや、「死ぬ危険性の高い行為」だと分かっていたかどうかを認定するのは困難だ。
一般的には、なぜ死んだかが特定できないのに、「死ぬ危険性の高い行為」を行ったのかどうかや、「死ぬ危険性の高い行為」だと分かっていたかどうかを認定するのは困難だ。
検察の起訴事実は、ある意味では「仮説」であり、立証責任は検察側にある。物証が少なく、判決が「日高氏の生命を奪った最終的な暴行の態様、その際の同人の身体の状況、暴行と死亡との間の具体的な機序が不明」と述べたのも無理はない。しかし、一方で、判決は、暴行による傷害によって死亡したという因果関係を傷害致死罪の範囲で認定した。暴行による傷害以外の原因で死んだ可能性を否定したことになる。
当時の出来事のほとんどすべてを知っている知佐被告人が、自分が無罪となるために構築した「彼女のなかの真実」の世界でも、「(古賀君と)同じことをやれば(日高君も)死ぬ」というのは自明のことだったと言える。だからこそ、公判で「同じことをやれば、(日高君も)死ぬと分かっていた。だから、古賀君が死んだ後は私は暴力を振るわなかった」と、殺害行為への関与を否定した(判決は、後段について信用性を否定し証拠から排斥した)。1人目の古賀氏の時ならいざ知らず、古賀氏が死んだのと同じことを繰り返しても「死ぬ危険性の高い行為」ではないと思っていたという主張が通るはずがないのは明らかだからだろう。
検察側「未必的殺意は優に認められる」
にもかかわらず殺意を認定できないとした判決は、通るはずのない主張を通すもので、「未必的殺意」の判断のあり方を後退させることにつながる。
確かに、古賀、日高両氏の死因や死亡時の状況はつまびらかではないので、「同じこと」をしたか否か、慎重な検討が必要だが、被告人が「同じことをやれば死ぬと分かって」いて、暴行を繰り返して死亡させたのに、「未必的殺意」が認定できないという判断は、今後の殺意のあり方に禍根を残す。検察側は、控訴にあたって、「殺人につき、少なくとも未必的殺意が優に認められるのに、これを認定せず、傷害致死とした原判決は、到底承服できない」とコメントした。長谷透次席検事は「公判の証言で、知佐被告人は、元従業員が死んだあと、同じことをやれば(日高氏も)死ぬと分かっていたと認めているのに、(判決が)未必的殺意を認めないのはおかしい」と、判決を批判した。
記者は、冤罪防止の観点に立って、二重の危険の原理(刑事被告人が同一の犯罪に対し二重の危険にさらされることを禁じる)から検察官上訴を禁止し、被告人を有罪にできる検察側の機会を1回に限定すべきだという主張を持っており、検察側の控訴に否定的だが、今回の判決を、殺意の認定の先例にすべきではない。控訴審では、被告人の意欲や動機という常識では解明できない内面にとらわれず、「未必的殺意」の有無に迫ってほしい。
(了)
【山本 弘之】関連記事
2024年4月8日 14:102024年4月3日 15:002024年4月1日 17:002024年4月18日 10:452024年4月15日 17:202024年4月5日 17:402024年4月18日 10:45
最近の人気記事
まちかど風景
- 優良企業を集めた求人サイト
-
 Premium Search 求人を探す
Premium Search 求人を探す
- 業界注目!特集
-
 産廃処理最前線
産廃処理最前線
サステナブルな社会を目指す
- MAX WORLD監修
-
 パーム油やPKSの情報を発信
パーム油やPKSの情報を発信
パームエナジーニュース







 一般的には、なぜ死んだかが特定できないのに、「死ぬ危険性の高い行為」を行ったのかどうかや、「死ぬ危険性の高い行為」だと分かっていたかどうかを認定するのは困難だ。
一般的には、なぜ死んだかが特定できないのに、「死ぬ危険性の高い行為」を行ったのかどうかや、「死ぬ危険性の高い行為」だと分かっていたかどうかを認定するのは困難だ。