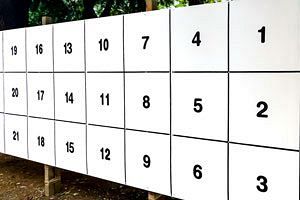昔、痴呆老人は「神」だった(後)
-

-
大さんのシニアリポート第49回
拙著『団地が死んでいく』(平凡社新書)でも触れたように、戦後、都市部に集中する人の住宅不足解消のため、公営住宅と公団住宅(現UR)を造った。とくに公団の目論見は、公団に入居した若夫婦は、やがて出世し経済的にも豊かになり、団地を出て戸建てを購入する。空いた部屋には再び若い夫婦が入居するという「団地の輪廻」という図式を描いていた。しかし、予測とは裏腹に成長した子どもたちは団地をでて、残された夫婦だけが団地で歳を重ねた。そこに「孤独死」の影が忍び寄る。団地(集合住宅)特有の遮蔽性、つながり(結、絆)のなさが孤独死を誘発してきた。
 実は、大正末から昭和初期にかけて建てられた「同潤会アパートメント」に「つながりを回避できる」ヒントが隠されていたのだ。拙著の中で引用した『同潤会に学べ』(内田青蔵著)に、「同潤会のアパートメントの持つ魅力の一つは、共同施設の存在であり、また、モダニズム建築とは異なった装飾性がまだ残る古めかしいデザインにあると思う。その共同施設こそ、すっかり忘れ去ってしまった“一緒に住む”“共同で住む”ということの意味を、われわれに問いかけているのであるそしてまた、今日、煩わしいものとして捨て去った共同施設こそ、一人で生きていけない人間の弱さを感じさせてくれるようにも思う」と的確に指摘している。戦後、都市への一極集中化にともなう住宅不足解消のために設けた超狭小住宅、いわゆる「ウサギ小屋」には、この同潤会アパートメントの精神は存在しなかった。つながりを持たないことが孤独死ばかりではなく、認知症という厄介な魔物も養成してきたのではないだろうかと思われてならない。
実は、大正末から昭和初期にかけて建てられた「同潤会アパートメント」に「つながりを回避できる」ヒントが隠されていたのだ。拙著の中で引用した『同潤会に学べ』(内田青蔵著)に、「同潤会のアパートメントの持つ魅力の一つは、共同施設の存在であり、また、モダニズム建築とは異なった装飾性がまだ残る古めかしいデザインにあると思う。その共同施設こそ、すっかり忘れ去ってしまった“一緒に住む”“共同で住む”ということの意味を、われわれに問いかけているのであるそしてまた、今日、煩わしいものとして捨て去った共同施設こそ、一人で生きていけない人間の弱さを感じさせてくれるようにも思う」と的確に指摘している。戦後、都市への一極集中化にともなう住宅不足解消のために設けた超狭小住宅、いわゆる「ウサギ小屋」には、この同潤会アパートメントの精神は存在しなかった。つながりを持たないことが孤独死ばかりではなく、認知症という厄介な魔物も養成してきたのではないだろうかと思われてならない。数年前「幸福亭」(「ぐるり」の前身)で実施したアンケートに、「子どもたちに迷惑をかけたくない」「子どもだって自分の家族がある」と気をつかう一方で、「せめてもの気持ちとしていくらかの財産を残していきたい」という言葉(財産という直接的な表現だけではなく、葬儀代、遺品整理代、墓地造成代など様々)が目についた。子どもへの負担を軽減する親の気持ちが込められているような気がする一方で、どうしても自分の介護の担保(期待)としての財産提供という本心を否定できなかった。はたして、「自分の子どもや孫が介護(自宅であれ、施設であれ)してくれるだろうか。自分を大切にしてくれるだろうか」。正直、その疑問は消えていない。
 丹羽文雄に『厭がらせの年齢』という、痴呆老人の置かれた立場、家族間の葛藤を描いた小説がある。文学博士で医療問題に詳しい新村拓は、『厭がらせの年齢』を引き合いに、「その介護を担っているのは第一次の団塊世代である。この世代はタテマエの残滓を引きずりながら、遠距離介護にも耐えている。だが、その子どもの世代ともなれば、親子の関係は親の世代に対する子どもの世代といった、集団のなかに位置づけられることになり、高齢者一般に対して自助努力を強く求めることになるであろう」(『痴呆老人の歴史』)と指摘している。
丹羽文雄に『厭がらせの年齢』という、痴呆老人の置かれた立場、家族間の葛藤を描いた小説がある。文学博士で医療問題に詳しい新村拓は、『厭がらせの年齢』を引き合いに、「その介護を担っているのは第一次の団塊世代である。この世代はタテマエの残滓を引きずりながら、遠距離介護にも耐えている。だが、その子どもの世代ともなれば、親子の関係は親の世代に対する子どもの世代といった、集団のなかに位置づけられることになり、高齢者一般に対して自助努力を強く求めることになるであろう」(『痴呆老人の歴史』)と指摘している。一緒に生活を共にしていない孫たちにとって祖父母は「死ぬまで面倒を看る」対象ではなく、単に「金や物をくれる打ち出の小槌」にすぎなく、孫の両親(つまり子どもたち)もまた「タテマエの残滓を引きずりながら」、本音では介護への忌避感を強く抱いているのが実情だ。では、どのようにすればいいのか。ヒントがあった。わたしの妻(67歳、現役介護専門学校生)の実習先(特養)では、面会に訪れる家族は数えるほどしかいないそうだ。ところが入所者もしたたか者で、実習生の妻を親しい間柄と勝手にみなし(大半が認知症)、気軽に話しかけ、様々な要求をだしてくるという。自宅での介護が叶わない場合には、施設を第二の故郷にして、そこに新しい家族(結)を作り上げる。つまり介護人を身内とみなす覚悟を持つことだ。最終的な”子離れ”である。施設という「姥捨て山」を逆手に取った発想で考えることが、ひとつの解答になると思う。
(つづく)
<プロフィール>
 大山眞人(おおやま まひと)
大山眞人(おおやま まひと)
1944年山形市生まれ。早大卒。出版社勤務ののち、ノンフィクション作家。主な著作に、『S病院老人病棟の仲間たち』『取締役宝くじ部長』(文藝春秋)『老いてこそ二人で生きたい』『夢のある「終の棲家」を作りたい』(大和書房)『退学者ゼロ高校 須郷昌徳の「これが教育たい!」』(河出書房新社)『克って勝つー田村亮子を育てた男』(自由現代社)『取締役総務部長 奈良坂龍平』(讀賣新聞社)『悪徳商法』(文春新書)『団地が死んでいく』(平凡社新書)『騙されたがる人たち』(近著・講談社)など。関連キーワード
関連記事
2024年4月8日 14:102024年4月3日 15:002024年4月1日 17:002024年4月18日 10:452024年4月15日 17:202024年4月5日 17:402024年4月18日 10:45
最近の人気記事
まちかど風景
- 優良企業を集めた求人サイト
-
 Premium Search 求人を探す
Premium Search 求人を探す
- 業界注目!特集
-
 産廃処理最前線
産廃処理最前線
サステナブルな社会を目指す
- MAX WORLD監修
-
 パーム油やPKSの情報を発信
パーム油やPKSの情報を発信
パームエナジーニュース







 実は、大正末から昭和初期にかけて建てられた「同潤会アパートメント」に「つながりを回避できる」ヒントが隠されていたのだ。拙著の中で引用した『同潤会に学べ』(内田青蔵著)に、「同潤会のアパートメントの持つ魅力の一つは、共同施設の存在であり、また、モダニズム建築とは異なった装飾性がまだ残る古めかしいデザインにあると思う。その共同施設こそ、すっかり忘れ去ってしまった“一緒に住む”“共同で住む”ということの意味を、われわれに問いかけているのであるそしてまた、今日、煩わしいものとして捨て去った共同施設こそ、一人で生きていけない人間の弱さを感じさせてくれるようにも思う」と的確に指摘している。戦後、都市への一極集中化にともなう住宅不足解消のために設けた超狭小住宅、いわゆる「ウサギ小屋」には、この同潤会アパートメントの精神は存在しなかった。つながりを持たないことが孤独死ばかりではなく、認知症という厄介な魔物も養成してきたのではないだろうかと思われてならない。
実は、大正末から昭和初期にかけて建てられた「同潤会アパートメント」に「つながりを回避できる」ヒントが隠されていたのだ。拙著の中で引用した『同潤会に学べ』(内田青蔵著)に、「同潤会のアパートメントの持つ魅力の一つは、共同施設の存在であり、また、モダニズム建築とは異なった装飾性がまだ残る古めかしいデザインにあると思う。その共同施設こそ、すっかり忘れ去ってしまった“一緒に住む”“共同で住む”ということの意味を、われわれに問いかけているのであるそしてまた、今日、煩わしいものとして捨て去った共同施設こそ、一人で生きていけない人間の弱さを感じさせてくれるようにも思う」と的確に指摘している。戦後、都市への一極集中化にともなう住宅不足解消のために設けた超狭小住宅、いわゆる「ウサギ小屋」には、この同潤会アパートメントの精神は存在しなかった。つながりを持たないことが孤独死ばかりではなく、認知症という厄介な魔物も養成してきたのではないだろうかと思われてならない。 丹羽文雄に『厭がらせの年齢』という、痴呆老人の置かれた立場、家族間の葛藤を描いた小説がある。文学博士で医療問題に詳しい新村拓は、『厭がらせの年齢』を引き合いに、「その介護を担っているのは第一次の団塊世代である。この世代はタテマエの残滓を引きずりながら、遠距離介護にも耐えている。だが、その子どもの世代ともなれば、親子の関係は親の世代に対する子どもの世代といった、集団のなかに位置づけられることになり、高齢者一般に対して自助努力を強く求めることになるであろう」(『痴呆老人の歴史』)と指摘している。
丹羽文雄に『厭がらせの年齢』という、痴呆老人の置かれた立場、家族間の葛藤を描いた小説がある。文学博士で医療問題に詳しい新村拓は、『厭がらせの年齢』を引き合いに、「その介護を担っているのは第一次の団塊世代である。この世代はタテマエの残滓を引きずりながら、遠距離介護にも耐えている。だが、その子どもの世代ともなれば、親子の関係は親の世代に対する子どもの世代といった、集団のなかに位置づけられることになり、高齢者一般に対して自助努力を強く求めることになるであろう」(『痴呆老人の歴史』)と指摘している。 大山眞人(おおやま まひと)
大山眞人(おおやま まひと)