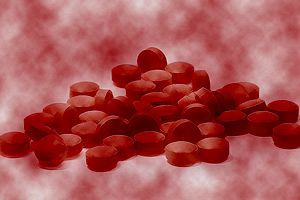誰が日本の高齢者を殺そうとしているのか(4)
-

-
第3回 夫婦ともに医療過誤! あり得ない現実に戸惑う仲間たち(前)
夫婦ともに医療過誤で殺されるという信じられない「事件」が起きた。徳井邦正(仮名)とは、小中同級で、近所に住んでいた関係から、別々の高校へ進学してからも、往き来していた幼友達、いわゆる「竹馬の友」である。結婚した徳井が、妻を医療過誤で亡くし、係争中だったことは知っていた。年に1,2回会い、杯を酌み交わしながら近況を報告し合っていた。その彼が、妻と同様医療過誤でこの世を去ったのだ。このあり得ない「事実」に言葉を失った。
新年の慌ただしさからようやく開放された2月1日、朝日新聞の朝刊を目にして、不思議な違和感を覚えた。「診断見逃し がん進行 慈恵医大、患者側に謝罪」という見出しで、「東京慈恵会医科大学病院(東京都港区)で、東京都町田市の男性患者(72)が肺がんの疑いを指摘された検査結果を主治医に見落とされ、約1年にわたってがんの治療を受けられなかったことが、病院などへの取材でわかった。男性は肺がんが進行し、家族によると現在、意識がないという」。町田市には知人が3人住んでいるが、同い年は徳井だけだ。不安がよぎる。
その日の午前中、松戸に住んでいる武村眞郞(仮名)から電話が入った。「新聞読んだ? アレ、徳井邦正のことじゃないか?」と電話口で早口にまくし立てる。武村のとっている新聞は産経新聞で、住所は明記していなかったが、「妻も医療過誤で亡くなっていると書いてあるんで、もしかしてと思い電話した」という。朝日と産経新聞を合わせてみれば、かなりの確率で徳井が浮かび上がる。「家族に連絡を取ってみる」という武村の声が遠くに響く。今年に限って賀状がこなかったことに一抹の不安を抱いてはいた。
数時間後、「間違いなく徳井だった。家族が証言した」と武村から電話が入った。「どうする?」「どうすればいい」「このままじっとしているのか?」「いや、どうにかしたい」。結局、面会に行くことにした。面会、といっても徳井に意識はない。徳井がベッドでどういう状況に置かれているのか、この目で確かめたいという強い欲求からだ。「自分の目で確認しないうちは、信じられない」と思った。 4日、新橋駅頭、蒸気機関車の前で午後3時に待ち合わせた。無言のまま慈恵医大病院へ急ぐ。ときおり吹く北風に足下をすくわれそうだ。10分ほどで、慈恵医大に到着。新聞発表後4日目なので、報道陣がいるのではないかという杞憂は霧消。守衛に目的を告げ、面会用の書類に必要事項を記入し、入館証を胸につけ、あっけないほどに簡単に入館ができた。ただ、そこから先が難題だった。徳井がいる集中治療室(ICU)の扉の前で待たされた。徳井の息子との連絡が取れず、ふたりの身分確認ができないという。連絡が付くまで待つしかない。約1時間後、「連絡が取れました」という報告があり、身分証明書を提示。荷物をロッカーに入れ、除菌等の処置をしたのち徳井のいるICUに案内された。
4日、新橋駅頭、蒸気機関車の前で午後3時に待ち合わせた。無言のまま慈恵医大病院へ急ぐ。ときおり吹く北風に足下をすくわれそうだ。10分ほどで、慈恵医大に到着。新聞発表後4日目なので、報道陣がいるのではないかという杞憂は霧消。守衛に目的を告げ、面会用の書類に必要事項を記入し、入館証を胸につけ、あっけないほどに簡単に入館ができた。ただ、そこから先が難題だった。徳井がいる集中治療室(ICU)の扉の前で待たされた。徳井の息子との連絡が取れず、ふたりの身分確認ができないという。連絡が付くまで待つしかない。約1時間後、「連絡が取れました」という報告があり、身分証明書を提示。荷物をロッカーに入れ、除菌等の処置をしたのち徳井のいるICUに案内された。
一番奥の部屋といっても、カーテンで仕切られただけの空間は、「個室」を連想させるにはほど遠い。徳井はベッドにいた。しかしそれは、想像以上に過酷な状態に置かれていた。ブドウ糖液、リンゲル液の袋、輸血用の袋、それに用途不明の袋がスタンドにつり下げられ、徳井の体全体を覆うようにチューブが絡みつく。鼻には酸素吸入器と思われる管が差し込まれ、口に入れられた管は痰の吸引のためだろうか。写真を撮ろうと思ったが、監視カメラがあると確信し思いとどまった。徳井は確かに呼吸らしきものをしていた。しかし意識はない。人間の耳は最後まで機能を持続させる器官だというが、目の前にいる徳井の耳に向かって今さら何を言えばいいのか分からない。無数の管が全身に突き刺さり、徳井を生かすために働いている。徳井は、こんなことを望んでいたのか。違うだろう。妻の無念を晴らすためにお前は先頭を切って運動してきたのではないか。
「2003年東京医大病院にて、IVHカテーテル誤挿入で配偶者が脳死状態となり、2年後死亡。病院は事件の隠蔽を図ったが、メディアがスクープして周知となる」(「東京医大被害者遺族ネット発足趣意説明」より)。徳井は数年間裁判を通して病院側と戦った。しかし、結局最後は和解となる。「妻に悪いことをしてしまった」と悔やんだ。その後、「医療過誤原告の会」の役員となり、「東京医大被害者ネットワーク代表世話人」として多忙な日々を送っていた。その徳井が、今、妻と同じ医療過誤で目の前にいる。若い看護士が痰の吸引の交換に来た。手慣れた段取りで口に吸引器を入れ、痰を吸引していく。ジュルジュル、ジュルジュル…。徳井が苦しそうに真っ赤な形相で身もだえた。そのとき何故か‘徳井が生きている’と思った。「意識が戻ることはないんでしょうね」「ありません」「会話は…」「できません」。看護師の明確な返答に何故か納得する。隣に座る武村と話を交わすことはない。武村と共有しているはずの時間は、多分わたしとは異質なものだろう。武村は徳井の裁判に足繁く通い、側面から支援してきた。目の前で粗い呼吸をくり返すだけの旧友にかける言葉を失ったように、悄然とたたずんでいる。「帰るか」という武村の声に我に返る。「また来てくださいね」という看護師の声に送られるようにICUから廊下に出た。「また来てくださいね」という若い看護師の思わず出た常套句に、苦笑した。また来てくださいか…。もう来ることはないだろう。新橋で呑み、御徒町に場所を移して痛飲した。それ以降のことは記憶にない。
(つづく)
<プロフィール>
 大山眞人(おおやま まひと)
大山眞人(おおやま まひと)
1944年山形市生まれ。早大卒。出版社勤務ののち、ノンフィクション作家。主な著作に、『S病院老人病棟の仲間たち』『取締役宝くじ部長』(文藝春秋)『老いてこそ二人で生きたい』『夢のある「終の棲家」を作りたい』(大和書房)『退学者ゼロ高校 須郷昌徳の「これが教育たい!」』(河出書房新社)『克って勝つー田村亮子を育てた男』(自由現代社)『取締役総務部長 奈良坂龍平』(讀賣新聞社)『悪徳商法』(文春新書)『団地が死んでいく』(平凡社新書)『騙されたがる人たち』(近著・講談社)など。関連記事
2024年4月8日 14:102024年4月3日 15:002024年4月1日 17:002024年4月25日 14:002024年4月15日 17:202024年4月5日 17:402024年4月25日 14:00
最近の人気記事
まちかど風景
- 優良企業を集めた求人サイト
-
 Premium Search 求人を探す
Premium Search 求人を探す
- 業界注目!特集
-
 産廃処理最前線
産廃処理最前線
サステナブルな社会を目指す
- MAX WORLD監修
-
 パーム油やPKSの情報を発信
パーム油やPKSの情報を発信
パームエナジーニュース







 4日、新橋駅頭、蒸気機関車の前で午後3時に待ち合わせた。無言のまま慈恵医大病院へ急ぐ。ときおり吹く北風に足下をすくわれそうだ。10分ほどで、慈恵医大に到着。新聞発表後4日目なので、報道陣がいるのではないかという杞憂は霧消。守衛に目的を告げ、面会用の書類に必要事項を記入し、入館証を胸につけ、あっけないほどに簡単に入館ができた。ただ、そこから先が難題だった。徳井がいる集中治療室(ICU)の扉の前で待たされた。徳井の息子との連絡が取れず、ふたりの身分確認ができないという。連絡が付くまで待つしかない。約1時間後、「連絡が取れました」という報告があり、身分証明書を提示。荷物をロッカーに入れ、除菌等の処置をしたのち徳井のいるICUに案内された。
4日、新橋駅頭、蒸気機関車の前で午後3時に待ち合わせた。無言のまま慈恵医大病院へ急ぐ。ときおり吹く北風に足下をすくわれそうだ。10分ほどで、慈恵医大に到着。新聞発表後4日目なので、報道陣がいるのではないかという杞憂は霧消。守衛に目的を告げ、面会用の書類に必要事項を記入し、入館証を胸につけ、あっけないほどに簡単に入館ができた。ただ、そこから先が難題だった。徳井がいる集中治療室(ICU)の扉の前で待たされた。徳井の息子との連絡が取れず、ふたりの身分確認ができないという。連絡が付くまで待つしかない。約1時間後、「連絡が取れました」という報告があり、身分証明書を提示。荷物をロッカーに入れ、除菌等の処置をしたのち徳井のいるICUに案内された。 大山眞人(おおやま まひと)
大山眞人(おおやま まひと)