
翌土曜日から倒産後の戦いが始まった。
営業系役員は朝10時から黒田会長を筆頭にオーナーへの説明会に当たった。
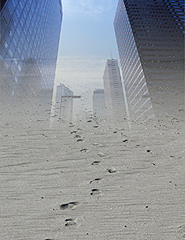 多くの人が当社の民事再生を知ったのは、金曜日の夜と考えられたので、土曜日の朝に速達が着くように計らい、10時から最初の説明会を開催したのだった。やはり準備は大切である。
多くの人が当社の民事再生を知ったのは、金曜日の夜と考えられたので、土曜日の朝に速達が着くように計らい、10時から最初の説明会を開催したのだった。やはり準備は大切である。
結局、土日それぞれ、午前中1回、午後1回の説明会を行ない、オーナーにサブリース家賃の送金ストップのお詫び(その分は敷金から引いてもらった)と、一般管理に切り替えていただければ来月からの家賃送金はまったく心配がないことを強調して、合意を取り付けるようにした。
幸いにも、7割方のオーナーに、やむを得ないと理解を示していただき、次々と一般管理への切替の同意書にサインをいただいた。やはり、創業者が福岡市中央区や南区というエリアで20年以上にわたって築いてきたオーナーとの信頼関係は簡単に薄れるものではないと思った。
ただ、なかには過剰な反応を示したオーナーもあった。
そのオーナーは、福岡市内でビジネスホテルなどを経営しており、事業の一環として当社より中古の貸しビルを購入し、その後当社は、そのビルの管理を受託していた。その人が、当社が民事再生を出した翌週明けに当社に乗り込んできた。
ちょうど私は、各役員に集まっていただきミーティングをしていたが、そこに営業課長が入ってきた。
「今、オーナーの●●さんが来社され、●●ビルの入居者の契約書と鍵を返せ、といって聞きません。お断りしているんですが、もう1時間も粘っています。お返ししてもよろしいでしょうか」と、慌てた様子で営業課長は述べた。
それを聞いて私は考えた。
企業として、取引先が経営危機に瀕した場合、必死で債権回収に走るのはわからないでもない。しかし、倒産前ならいざ知らず、当社はすでに民事再生を出して裁判所の監督下に入っている。しかも、民事再生直後の家賃は支払ストップしたものの、その分、差し入れている敷金から差し引いていただけるので迷惑を掛けないこともお伝えしている。翌月以降も裁判所の監督の下、家賃の支払は問題なく続けられる。そのようなことをお伝えした結果、大半のオーナーは、心配しながらもサブリースの一般管理への切替を受け入れようとしているのに、このように一部の横暴を許すと、そこから取付騒ぎが広がり、民事再生そのものが成り立たず、事業継続を断念して破産、ということになりかねない。それでは、善良なオーナーにも迷惑が掛かる。
そこまで考えたら、自ずと正しい対応を組み立てることができた。
「いま、裁判所から保全命令が出ていて、入口にその旨貼ってあるはずだ。そのオーナーがいわれることは保全命令に違反するので受けることはできない。オーナーが犯罪者になってしまうので、その旨説明して帰ってもらうように」
私はこのように述べ、このオーナーにはお引取り願った。
が、それだけで気が済まなかったのか、この人は翌日、自社の銀行口座の番号を記し「家賃の振込先が変わりました」というチラシを作成し、自分のビルの入居者に配り始めた。
それでも、当社は民事再生の直後から入居者への案内などをきちんと行なっていたため、大半の入居者にこれまでどおり家賃入金をいただいたが、一部は、「どちらに振り込んでいいかわからず、紛争に巻き込まれるのはご免だ」という気持ちから、家賃をどちらにも振り込まず法務局への供託を行なった。
このオーナーとは、弁護士も介入し、ひとかたの紛争になったが、弁護士が入れば民事再生法に従わざるを得ず、最終的には、契約上の違約金額に予想配当率を乗じた額を支払うことで平和裏に管理契約を解約した。
▼関連リンク
・REBIRTH 民事再生600日間の苦闘(1)~はじまり
<プロフィール>
石川 健一 (いしかわ けんいち)
東京出身、1967年生まれ。有名私大経済学卒。大卒後、大手スーパーに入社し、福岡の関連法人にてレジャー関連企業の立ち上げに携わる。その後、上場不動産会社に転職し、経営企画室長から管理担当常務まで務めるがリーマンショックの余波を受け民事再生に直面。倒産処理を終えた今は、前オーナー経営者が新たに設立した不動産会社で再チャレンジに取り組みつつ、原稿執筆活動を行なう。職業上の得意分野は経営計画、組織マネジメント、広報・IR、事業立ち上げ。執筆面での関心分野は、企業再生、組織マネジメント、流通・サービス業、航空・鉄道、近代戦史。
※記事へのご意見はこちら
