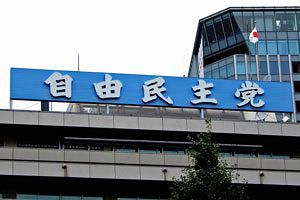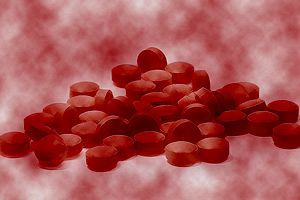【熊本地震】M7.3強襲!!記者が体験した被災地の真実(1)
-

-
最大震度7の地震がほぼ1日おきに発生し、甚大な被害を与えた平成28年熊本地震。地震発生後の避難生活のなかで、被災地の人々はどのような不安を抱えていたのか。その内情を知らなければ、必要な支援を行うことも、今後の地震災害に備えて教訓化していくことも難しいだろう。震災から3カ月が経った今、本震の発生(4月16日)から約1週間を被災地の実家で過ごした記者が、当時の状況を被災地の視点で振り返る。
恐怖すら奪う激震
 4月14日午後9時26分に発生した熊本地方の地震を受けて、翌朝(4月15日)、筆者は熊本市西区二本木の実家へ向かった。福岡市を出たのは朝8時過ぎ、すでに高速道路は南関インターで通行止めとなっており、途中から渋滞する下道で熊本を目指す。実家に着いたのは昼過ぎ。一見すると、建物自体は無事であり、迎え出た両親の姿を見て一安心した。
4月14日午後9時26分に発生した熊本地方の地震を受けて、翌朝(4月15日)、筆者は熊本市西区二本木の実家へ向かった。福岡市を出たのは朝8時過ぎ、すでに高速道路は南関インターで通行止めとなっており、途中から渋滞する下道で熊本を目指す。実家に着いたのは昼過ぎ。一見すると、建物自体は無事であり、迎え出た両親の姿を見て一安心した。家のなかは散々な有様だった。重量のある家具が倒れ、花瓶や食器などのガラス類が割れて飛散し、足の踏み場もない状況だった。ただ、水道はつながっており、その日は、入浴することもできた。テレビでは気象庁の役人が、「平成28年(2016年)熊本地震」と命名したことを発表し、「震度6弱の余震が発生する確率は20%」という予測を伝えていた。その間も余震とされる揺れが続いていたが、「あれ(14日の地震)以上の余震が来るはずはない」と思っていた人は少なくはなかっただろう。実際に、実家周辺では15日の夜は家のなかにいたという住民がほとんどだった。
4月16日午前1時25分、「ドシン!」という凄まじい音に起こされた。地響きと家が激しく軋む音のなか、地面から突き上げるような縦揺れと立つことさえもままならぬ横揺れが襲ってきた。頭の中が真っ白になり、何が起きているのかわからなかった。恐怖を感じる余裕がなかった。
ようやく地震であることが認識でき、壁が倒れ、天井が落ちてくるのではないかという恐怖に襲われた。寝ていた時に足が向いていたほうへ目をやると、最初の地震ではビクともしなかった重い本棚が寝床に覆い被さるように倒れていた。頭の向きを逆にして寝ていたら一巻の終わりだったかもしれない。それが後に「本震」とされたマグニチュード7.3の地震の発生時の記憶である。
 <
<2階の天井が崩落した益城町公民館
少しずつ揺れが収まると、家の外から「大丈夫ですか!」という近所の住民の安否確認の声が届いた。暗闇のなか、家族で名前を呼び合い、無事を確認しながら外へ出た。向かった先は、近くにある企業の駐車場。倒壊のおそれがある建物を避けて避難した。誰かが、地区の避難所である小学校の名前を出したが、「あそこは老朽化しているから危ない」という声がその選択肢を打ち消した。
駐車場には隣近所の人々が皆、着の身着のままで続々と集まっていた。14日の前震の際もこの場所に集まり、集団で夜を過ごしたという。その時の経験が活きたのだろう。人々は大した混乱を見せず、続々と駐車場に集まってきた。本震が発生した時が晴天であったことや、少し肌寒いくらいの気温であったことは、まさに“不幸中の幸い”だった。
しかし、その後も頻発した震度3~5の地震に苛まれた。揺れが起きる度に悲鳴があがった。最大の恐怖は電柱の倒壊だった。被害を抑えるため、電力会社が電気を落とすことは聞いていたが、倒れてくる電柱をまともに受ければひとたまりもない。地震が起きる度に、それぞれが四方に目をやり、警戒を続けた。とても眠る余裕はない。周囲に目を配り、励まし合いながら数時間が経過。余震の合間をぬって、それぞれが自宅に寝具と車を取りに行った。車中泊生活の始まりである。
(つづく)
【山下 康太】関連記事
2024年4月8日 14:102024年4月3日 15:002024年4月1日 17:002024年4月25日 14:002024年4月15日 17:202024年4月5日 17:402024年4月25日 14:00
最近の人気記事
週間アクセスランキング
まちかど風景
- 優良企業を集めた求人サイト
-
 Premium Search 求人を探す
Premium Search 求人を探す
- 業界注目!特集
-
 産廃処理最前線
産廃処理最前線
サステナブルな社会を目指す
- MAX WORLD監修
-
 パーム油やPKSの情報を発信
パーム油やPKSの情報を発信
パームエナジーニュース







 4月14日午後9時26分に発生した熊本地方の地震を受けて、翌朝(4月15日)、筆者は熊本市西区二本木の実家へ向かった。福岡市を出たのは朝8時過ぎ、すでに高速道路は南関インターで通行止めとなっており、途中から渋滞する下道で熊本を目指す。実家に着いたのは昼過ぎ。一見すると、建物自体は無事であり、迎え出た両親の姿を見て一安心した。
4月14日午後9時26分に発生した熊本地方の地震を受けて、翌朝(4月15日)、筆者は熊本市西区二本木の実家へ向かった。福岡市を出たのは朝8時過ぎ、すでに高速道路は南関インターで通行止めとなっており、途中から渋滞する下道で熊本を目指す。実家に着いたのは昼過ぎ。一見すると、建物自体は無事であり、迎え出た両親の姿を見て一安心した。 <
<