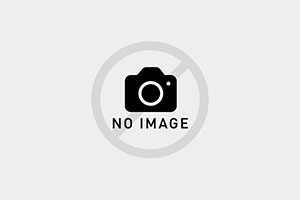(株)武者リサーチ
代表 武者陵司 氏

2024年春、トランプ政権が突如発表した「相互関税」により世界の株式市場は一時急落したが、その後の米中合意や経済政策の明確化により、米国株は急速に回復した。通商秩序の破壊やドル体制崩壊への懸念は払拭され、トランプ政権の「市場第一主義」的な柔軟姿勢がむしろ投資家に安心感を与えた。「資本主義ファースト」という信念のもと、関税政策と株高の共存が再評価されるなか、長期的な米国株上昇へのシナリオが再浮上している。
なぜトランプ政権のもと株高が期待できるのか
相互関税ショックと株価のV字回復
4月2日のトランプ政権の意表を突く大相互関税発表によるショックで急落した主要国株価は、5月12日の米中関税暫定合意以降完全に元に戻った。米国S&P500指数は、2月19日の史上最高値(6,144)から4月8日の大底(4,982)まで19%の大暴落となったものの1カ月後の、5月19日には大底から19%上昇の5,963となり、年初比でもプラスに浮上した。国際通商秩序が破壊され大不況に陥るという最悪シナリオはほぼ否定された。
唐突の相互関税発表時点ではその目的として、1)製造業を取り戻すこと、2)貿易赤字を減らすこと、3)税収を増やすこと、4)相手国の譲歩を求める手段とすること、の4つの狙いが考えられた。投資家の頭によぎった悪夢は、国際分業体制を否定してしまうのか、ドル体制を壊してしまうのかという極論であった。製造業製品の8割以上を輸入に頼っており米国国内での供給力がまったく存在していない状態で輸入を遮断すれば、米国民の生活が立ち行かなくなる。関税の価格転嫁と供給不足によるインフレも心配される。
また米国の輸入代金(=赤字)は世界に対する基軸通貨ドルの供給であるため、米国の赤字がなくなることとは、世界経済に対する成長通貨の供給停止を意味する。どちらも世界経済体制を根底から揺るがすことになる。
だがこれらの極論は一連の展開により否定された。米国が確保したいものは先端ハイテクと軍事装備品、医薬品などライフラインに関わる製造業であり、すべてを戻すことはまったく考えていないことがわかった。
また通貨安により米国の赤字削減を狙うことは、直ちに米国への資金流入の減少と米国金利上昇を引き起こし、リセッションをもたらす縮小均衡の道である。ベッセント財務長官はトランプ政権がその路線を取らないことを、繰り返し表明し、市場の疑心を払拭した。
そうなると、トランプ関税は株高要因にもなり得るというシナリオが浮上する。ベッセント氏はアベノミクスの3本の矢を模して、Trump’s Three Steps to Economic Growthを発表した。
第1ステップは、国際貿易の再交渉により製造業の雇用を大量に取り戻すこと、第2ステップは2017年の減税・雇用法を恒久化し、設備投資の100%即時償却を復活させ、再工業化を加速するために新工場建設にも優遇措置を拡大すること、第3ステップは規制緩和を半導体、発電所、AI(人工知能)データセンターその他の未来のテクノロジー、エネルギー開発、金融機関やその他の小規模銀行などで実施することである。
これらにより米国経済は成長を続け、中国への依存度は低下し、エネルギー価格は下落し、財政赤字は減少し、ドル安は回避されるという可能性が開けてくる。
支持基盤の分裂も基本姿勢は市場第一主義
それにしても4月以降の株価の乱高下と、その背景にあるメディアや専門家の間でのトランプ氏やトランプ政権の政策に対する批判と懸念は行き過ぎだった。2つの理由がある。第1はメディアや多くの専門家が最初から民主党寄りで反トランプなので、トランプ政策はそもそも失敗するはずだ、失敗すべきだというバイアスが存在していることである。しかし第2にトランプ政権内にも懸念されるべき理由がある。それは政権を支持するグループの主張のなかに、経済合理性にそぐわず株価を引き下げる要素が内包していることだ。
まず心配されるのは保守派ナショナリストグループが主張する、反グローバルという頑なな理念である。グローバリズムは中国の台頭を引き起こし災いを大きくしたが、国際分業がすべて問題というのは飛躍である。米国は最も生産性が高いハイテクに特化し、付加価値が低い製品を海外に依存するというWin-Winの関係も存在する。なにより米国企業そのものがこのグローバルサプライチェーンの受益者である。次に心配されたのは反ウォール街、反国際金融という意見だ。プラザ合意に類似する第2弾のドル安合意もいとわないという政策(マールアラーゴ合意)も、米国が享受し続けてきたドル覇権の棄損に結びつきかねない暴論である。
しかし政権内ではグローバリストと目されるウォール街金融の出身者であるスコット・ベッセント財務長官やハワード・ラトニック商務長官が財政金融政策を仕切り、市場の安定と金融秩序を維持しつつと経済成長のかじ取りをしている。さらにトランプ支持グループとして政府効率化省(DOGE)ヘッドであったイーロン・マスク氏など富裕なテクノリバタリアンが関与し、行政機構の改革、財政費用削減、規制緩和に大ナタを振るっている。これらのグループは、保守ナショナリストとは主張が異なり関税や移民排除に必ずしも賛成でないグローバリストの側面ももっている。たとえば関税引き上げを主導したピーター・ナバロ大統領上級顧問とイーロン・マスク氏の対立は広く報道された。トランプ氏は、主張の異なるいくつかの支持グループを巧みに操りながら、経済成長を持続させつつ大改革を遂行しているのである。
だが、先述の通り、市場がクラッシュしたら直ちに政策変更したことから、トランプ氏の姿勢は成功するためには株価維持が必須であり、市場が容認しない政策は変更するというスタンス、つまり市場第一主義であることがはっきりした。このように柔軟なトランプ政権において揺るぎない政策の肝があるとすれば、それは「米国資本主義の隆盛」であろう。あえてトランプ氏の心中を推測すれば、「資本主義ファースト、資本主義亡き民主主義は虚構」と考えているのだろう。このように見ると、米国株価の長期上昇トレンドは変わらないという想定が再びメインシナリオに戻ってくるのではないだろうか。
潜在力大きい日本株 今のところ1人負けだが
好循環が呼ぶ株高と自社株買いバブル
2025年から26年にかけて、日本株式が再度世界の注目を集める場面が出てくるだろう。日経平均は5万円が視野に入ってくると思われる。1ドル140~160円の円安レンジが定着しデフレ完全脱却が見えてくるだろう。政策次第で長期低落してきた日本の潜在成長率が、上昇に転ずる可能性が十分に考えられる。5%近い高賃上げの継続で消費が上向く。設備投資とマンションブーム、ホテルブームで建設業が久しぶりに活況を呈している。外国人観光客の急増が津々浦々の地方経済を潤している。中国に見切りをつけた企業の日本回帰や、海外企業の対日投資はTSMC熊本やラピダス千歳の先端半導体工場建設に続き、本格化していくなど好循環の種が整っている。
こうした好環境の下で、企業の自社株買いの大ブームが起こっている。東証調査による法人の株式購入(その大半は自社株買い)は22年12.6兆円23年14.3兆円、24年21.6兆円と急増しており25年には30兆円に迫っていくと予想される。このスケールでの自社株買いは日本株の株式需給を根本的に改善していくと思われる。ちなみに23年以降の日本株ブームを主導した外国人の買いは先物、現物合わせて8兆円であったが、昨秋の乱高下場面で外国人は12兆円を売却してしまった。この外国人売りにもかかわらず日本株が高値圏を維持できたのは企業の旺盛な自社株買いが続いたからである。
実は自社株買いは米国経済成長と米国株高の陰の主役であった。米国株式はリーマン・ショック後のボトムから15年間で8倍(年率15%)の急上昇を遂げ、家計の純資産を59兆ドルから160兆ドルへと100兆ドル(=GDP比3.6倍)押上げ、米国の旺盛な消費を牽引してきた。では誰が株価を押し上げたかというとそのほぼすべてが自社株買いであった。この間企業は累計で5.4兆ドル株を購入し年金・保険の巨額の売りを米国が吸収し続けたのである。
AI革命など歴史的技術発展の時代に、企業収益が高まり、企業部門に過剰利益が蓄積されている。この企業利益を経済システムに還流させるうえで、自社株買いが大きな役割をはたしてきたのである。この資金の流れは、株式市場を通じてベンチャーに巨額の投資資金が集まるエコシステムづくり上げ、米国ハイテク技術制覇の原動力にもなった。まさしく米国では株式市場が企業の利益還元を通して、資源配分を采配する「株式資本主義」の時代に入っている。そしてトランプ政権は「株式資本主義」を政策プラットフォームとして強化しようとしている。
株式資本主義への転換と企業行動の変貌
ではそのような「株式資本主義」がいつ何によって起こったかというと、それは1980~90年代の米国の企業買収ブームであった。今の日本に同様の動きが起きている。東証・金融庁によるPBR1倍以下の企業の是正要求、日経新聞の「私の履歴書」へのKKR創業者ヘンリー・クラビス氏(30年前は米国でも野蛮人といわれていた)の登場など、日本の政策と企業社会はM&A受容へと驚くばかりの姿勢変化を見せた。カナダ企業であるアリマンタシォン・クシュタール(ACT)によるセブン&アイ・ホールディングスの買収提案は、資本の効率性をないがしろにし、低株価を放置してきた日本の株式市場に大きく活を入れるものになった。
時価総額44兆円の日本最大企業のトヨタですら買収のターゲットになり得る。販売台数ではトヨタの6分1のテスラは、マスク氏のトランプ政権協力に対する不買運動で株価が半減した後でも株式時価総額では1兆ドル(150兆円)とトヨタの3.6倍の規模にあり、M&Aの餌食になりかねないのである。昨年トヨタが11%であるROE(自己資本利益率)を20%に引き上げると発表して市場を驚かせたが、巨額のキャッシュを抱えて安閑としてはいられなくなったのである。また最大株主豊田自動織機(9%保有)の非上場化も敵対的買収に対する備えと見られる。このようにして日本は米国で確立した「株式資本主義」に急速にシフトし、一大自社株買いブームが起き始めている。
日本株式は株式益回り6%、国債利回り1.4%と国債に比して著しく割安であるが、その割安さは企業による自社株買いと配当増による株主還元によって、是正されていくだろう。そしてこの株高はNISAを通して資産運用を高め始めた家計、いったん購入した日本株を売り切った外国人、GPIFに準じて積極運用を政府から求められている公的年金機関など多くの投資主体の日本株買い意欲を高める可能性は高い。日本株式は依然として力強い長期上昇の過程にあると言ってよい。
政治が変わるかが鍵
家計を直撃した高負担と消費低迷の現実
とはいえ2024年8月の植田日銀の利上げ、タカ派転換による株価急落以降、日本株は再び世界市場のなかで最悪に近いパフォーマンスになっている。日本の政策に対する不信感がグローバル投資家の日本株購入意欲を削いでいる。不信感の最大の要因は日本経済の低成長である。上述のさまざまな好条件がありながらも、日本経済の成長率はG7のなかで最低水準に落ち込んだ。IMFによる見通し(4月時点)は、24年0.1%(米国2.8%、ユーロ圏0.9%)、25年0.6%(米国1.8%、ユーロ圏0.8%)となっている。
最大の理由はGDP最大項目消費の低迷である。家計実質消費は14年3月の消費税増税(5⇒8%)直前の14年1~3月の310兆円がピークで、その後一度もそれを上回らず依然として10年前のピークに比べ4%減の水準にある。この間企業利益は2.4倍、株式時価総額は3.2倍、一般会計税収は1.6倍になったわけで、家計が1人犠牲にされてきたといえる。
なぜ消費が1人取り残されてきたのか。一般的には賃金が上がらず実質家計所得が伸びなかったとされているが、賃金は24年春闘以降3~5%と上昇に転じている。賃金以上に家計を直撃したのが、増税と社会保険負担の上昇による高負担である。12年に成立した「社会保障と税の一体改革」は当時の民主党野田首相のもとで民主・自民・公明の3党合意として結実し、安倍内閣での不本意の2度の消費税増税を実現させた。「一体改革」導入前の11年の国民負担率(国民所得に対する租税と社会保険料負担率)は38.8%と低かったが22年には48.4%と世界にも例のない急上昇となり、家計消費を直撃したのである。
財政健全化の実態と政策転換の必要性
この高負担路線は現在も進行している。直前の国会で成立した年金改革法は高負担・財政健全化路線そのものといえる。具体的内容は、①国民年金の不足(就職氷河期の人々に対する給付を保証するために)を厚生年金資金で補てん、②遺族年金の減額、③パート労働者への厚生年金の適用(家計と企業負担増)など、負担増給付減の法案であり、将来給付に欠損が生じた場合に消費税増税が正当化されることになる。
また少子化対策の一環として26年4月からスタートする「子ども・子育て支援制度」も、保険料を引き上げるステルス増税とみられる。独身者に対する不公平感から「独身税」と俗称されている。年収に対して28年度には平均で0.2%の社会保険負担増になるが、それは年間社会保険料の5%増額と計算されており、消費税0.8%増税に相当するとの指摘がある。
しかし他方、増税とインフレにより税収が大きく上振れしている。政府は税収増を隠すかのように毎年定額減税や給付金で財政改善の実態をわかりにくくしているが、もはや隠し切れない規模に膨らんでいる。23年度税収実績72兆円に対して24年度は76兆円と当初予算を6兆円強上回った模様、25年度には80兆円に達すると見られ、恒久減税の財源が十分であることは明らかであろう。
また日本の財政はギリシャ以下との石破首相の発言は誤りである。財務省が示す政府総債務は1,473兆円でGDP比は、237%と世界最悪だが、日本はほかのどの国よりも多くの資産をもっている。外為会計による巨額の米国国債、巨額のGPIF運用益、高速道路など収益を生む固定資産、事業収入のある各種特殊法人への貸付など、連結ベースで見れば1,048兆円の資産をもっている。この資産を差し引いた連結ベースでみた政府の純債務は528兆円、対GDP比89%となり、G7の平均よりも良好である。
さらにより客観的な財政健全化指標である、政府の純利払い費のGDPに対する割合は、日本が0.6%とG7中最低水準である。日本の財政はどこから見ても健全なのである。このように、①増税と高社会保険料負担により、家計だけが犠牲になってきたこと、②税収増により家計に対する財政援助の余力が高まっていること、③日本の財政は世界のなかでも健全であること、は明らかである。
このように政策転換により高負担路線が修正されることが国民生活、経済成長と株価に必須の条件であるといえる。緊縮財政からの転換でドイツ株が2割の急騰を見せたように、日本株の展望は選挙後の政策の枠組みで大きく変わり得ることを強調したい。
<PROFILE>
武者陵司(むしゃ・りょうじ)
 1973年横浜国立大学経済学部卒業後、大和証券に入社。88年大和総研アメリカでチーフアナリストとして米国のマクロ・ミクロ市場を調査。97年ドイツ証券調査部長兼チーフストラテジスト2005年ドイツ証券副会長を経て、09年(株)武者リサーチを設立。21年9月までドイツ証券(株)アドバイザーを務める。日経電子版、日経産業新聞(眼光紙背)、WILL、Voice、四国新聞社、月刊資本市場、投資経済、統計、外為どっとコム、幻冬舎ゴールドオンライン、週刊エコノミストなどにレポートやコラムを寄稿。テレビ朝日、BS11、日経CNBC、テレビ東京モーニングサテライト、BSフジプライムニュース、ストックボイス、ラジオNIKKEI、文化放送などにコメンテーターとして出演。
1973年横浜国立大学経済学部卒業後、大和証券に入社。88年大和総研アメリカでチーフアナリストとして米国のマクロ・ミクロ市場を調査。97年ドイツ証券調査部長兼チーフストラテジスト2005年ドイツ証券副会長を経て、09年(株)武者リサーチを設立。21年9月までドイツ証券(株)アドバイザーを務める。日経電子版、日経産業新聞(眼光紙背)、WILL、Voice、四国新聞社、月刊資本市場、投資経済、統計、外為どっとコム、幻冬舎ゴールドオンライン、週刊エコノミストなどにレポートやコラムを寄稿。テレビ朝日、BS11、日経CNBC、テレビ東京モーニングサテライト、BSフジプライムニュース、ストックボイス、ラジオNIKKEI、文化放送などにコメンテーターとして出演。