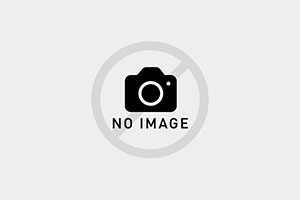5月23日の参議院本会議において、マンションの管理・再生の円滑化等のための改正法案が可決、成立した。出席者多数決による決議・運営の円滑化、分譲事業者による管理計画の認定申請などマンション管理の適正化と、建替え以外の手法による新たな再生手法の創設が柱となる。区分所有法など関係する法律の改正は、一部を除いて2026年4月から施行される。
管理計画認定を後押し
改正法は、マンションの老朽化と住民(区分所有者)の高齢化という、いわゆる「2つの老い」問題に対応したものだ。マンションの大規模修繕や建替え、売却などには住民の意思決定が必要になってくるが、高齢住民の負担が大きいことで意思決定が進まない高経年マンションが増えることが予想されている。国土交通省によると、築40年以上のマンションは2023年末時点で約137万戸だが、10年後の33年末には約274万戸、20年後の43年末には約464万戸まで増えると予想されている。
外壁の剥落など管理が行き届かないマンションを減らし、必要な修繕や建替えを促すことは、喫緊の課題といえる。今回の改正では、マンション管理の適正化と新たな再生手法の創設の2つが大きな柱となっている。これらについて、順番に見ていこう。
まずマンション管理の適正化については、マンション管理計画認定制度の充実と管理業者管理者方式への対応、集会決議の円滑化、マンション等に特化した財産管理制度が挙げられる。管理計画認定制度の充実の具体策として、マンションデベロッパーが新築時に策定した認定管理計画を、新たにできた管理組合に引き継ぐ制度が導入される。管理計画認定制度は、マンション管理の質を高めるため、一定の基準を満たすマンションの管理計画を地方自治体が認定する制度。認定を受けると、固定資産税の減免などを受けることができる。
通常は、管理組合の管理者(理事長)などが申請をすることになる。管理組合が発足していない新築マンションの場合、現行ではマンションデベロッパーや管理会社が管理計画を策定して予備認定を取得し、管理組合の発足後に改めて予備認定から本認定に変更する制度がある。しかし、本認定への変更が進んでいないため、認定する自治体からも改善を求める声が出ていた。そこで、マンションデベロッパーも認定申請を可能にすることになる。
この措置によるマンション市場への影響は限定的だが、管理不全のマンションを減らす効果はあるのではないか、と評価する専門家の声もある。...

月刊まちづくりに記事を書きませんか?
福岡のまちに関すること、建設・不動産業界に関すること、再開発に関することなどをテーマにオリジナル記事を執筆いただける方を募集しております。
記事の内容は、インタビュー、エリア紹介、業界の課題、統計情報の分析などです。詳しくは掲載実績をご参照ください。
記事の企画から取材、写真撮影、執筆までできる方を募集しております。また、こちらから内容をオーダーすることもございます。報酬は別途ご相談。
現在、業界に身を置いている方や趣味で建築、土木、設計、再開発に興味がある方なども大歓迎です。
また、業界経験のある方や研究者の方であれば、例えば下記のような記事企画も募集しております。
・よりよい建物をつくるために不要な法令
・まちの景観を美しくするために必要な規制
・芸術と都市開発の歴史
・日本の土木工事の歴史(連載企画)
ご応募いただける場合は、こちらまで。不明点ございましたらお気軽にお問い合わせください。
(返信にお時間いただく可能性がございます)