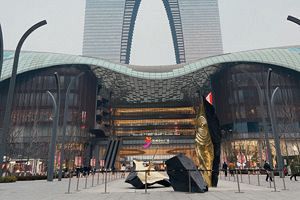経済に関する国際ニュースを厳選して配信。
2023年6月24日 06:00
中国政府が6月6日に発表した「2023中国インターネットオーディオ・動画発展研究報告」によると、2022年12月の時点で、中国のインターネット視聴ユーザーは10億4,000万人...
2023年6月23日 06:00
最近、コカ・コーラ値上げのニュースが業界で注目を集めている。実際にはコーラだけの現象ではなく、原材料コスト上昇などの影響により、今年に入ってからすでに複数の飲料品メーカーが商品の値上げを発表した。
2023年6月22日 06:00
世界最大の自動車市場の中国で電気自動車(EV)の競争が激しくなってきた。比亜迪(BYD)といった中国勢と米テスラなどの欧米勢がしのぎを削り、2割値下げする動きもある。
2023年6月21日 09:50
暗号資産取引所のバイナンスがアメリカ証券取引委員会から訴えられた後、「証券」と指定されたコインは軒並み二桁ほどの価格下落に見舞われた。
2023年6月20日 16:45
台湾のフラッグキャリアのチャイナエアラインは19日、熊本と台北(桃園国際空港)を結ぶ定期便を9月から就航させると発表した。
2023年6月20日 15:35
(株)データ・マックスの児玉直会長は19日、福岡市を訪れた香港の金融機関・BM Intelligence グループの盧華威(ローウェル・ロー)会長(香港公認会計士)と意見交換を行った。
2023年6月20日 11:30
暗号資産が取引可能な金融商品である「証券」に相当するか否か、議論が続けられているが、それに対する明確な解釈はいまだ提出されていない。
2023年6月19日 12:30
時の経つのは速く、安倍元首相が世を去って間もなく1年になる。
2023年6月19日 06:00
現在、アメリカを覆う「分断と分裂」の嵐を見るにつけて、1968年と2023年の類似性を感じざるを得ません。1968年といえば、ベトナム戦争の真っ最中でした。
2023年6月18日 06:00
ブルーボトルコーヒーやピーツ・コーヒー&ティーといった海外のコーヒーブランドが近年、続々と中国市場に進出すると同時に、中国ですでに根付いている海外ブランドも勢いを増している。
2023年6月17日 06:00
最近の数年間、コーヒー産業は大きく上昇してきた。中国市場調査会社「満幇」のデータでは、2022年のコーヒー輸送量は10月と12月にピークを迎え、とくに12月は前月比30%以上増加した。
2023年6月16日 06:00
中国では昔から、結婚前にマイホームを購入するというのが伝統的な観念としてある。では、なぜ多くの人が「結婚前にマイホームを購入しておかなければ」と考えているのだろうか?
2023年6月15日 16:00
コロナ禍という長いトンネルを抜け、2023年の今年、カンボジア地雷撤去キャンペーン(CMC)は創立25周年を迎えました。
2023年6月14日 09:40
米欧諸国にとって最大課題のウクライナ問題はどうだった。5月20日にゼレンスキー・ウクライナ大統領が広島に到着してから、広島サミットはさながらゼレンスキーに「支配された」(インド紙「インディアン・イクスプレス)。
2023年6月14日 06:00
日本政府が半導体製造措置などの輸出規制を発表したことについて、中国商務部(省)の報道官は5月23日、「日本は直ちに誤ったやり方を是正すべきで、中国は措置を取る権利を留保する」述べた。
2023年6月13日 17:00
AIが未来のIT産業の地形を変えるコア技術として注目が集まるにしたがい、AI半導体に各社から熱い視線が注がれるようになった。