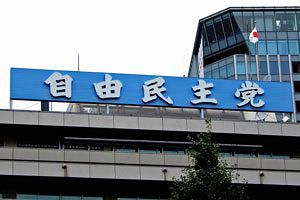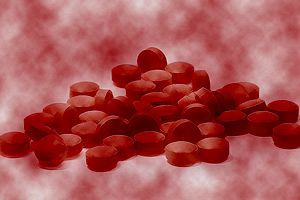【凡学一生のやさしい法律学】憲法改正について(4)
-

-
 自由心証権とは裁判官に証拠の評価について自由な裁量権を認めた訴訟法レベルの規範です。この規定によって裁判官が自由に証拠の評価をすることは、正に法律の規定に従っているという意味では外形的・形式的には「適正手続」です。しかし、証拠の評価は科学的で合理的なものでなければならず(証拠裁判主義)、裁判官が自由に心証で評価できるという規定自体が、非科学的で不合理です。これは裁判官を神として認めるようなもので、日本司法の冤罪・誤判の根本原因です。
自由心証権とは裁判官に証拠の評価について自由な裁量権を認めた訴訟法レベルの規範です。この規定によって裁判官が自由に証拠の評価をすることは、正に法律の規定に従っているという意味では外形的・形式的には「適正手続」です。しかし、証拠の評価は科学的で合理的なものでなければならず(証拠裁判主義)、裁判官が自由に心証で評価できるという規定自体が、非科学的で不合理です。これは裁判官を神として認めるようなもので、日本司法の冤罪・誤判の根本原因です。この裁判官の自由心証権こそ証拠法における後進性、前時代性を代表するものですが、法学界でこの不合理がまともに議論されたことはありません。日本の法律学の後進性、低文明性の根本原因です。これを長年示してきたものが判例公表のスタイルです。日本の大審院時代からの膨大な判例の集積は、科学的認識論からみれば、紙くずの集積です。なぜなら、判例集の法的評価の前提となる認定事実には何らの根拠(証拠)がなく、すべて、裁判官が自由心証で認定した事実を前提に法律論が展開されているに過ぎないからです。
このいわば裁判官の自画自賛の判決を、日本の代表的な法学者集団である東京大学法学部出身学者の学術団体である法学研究会が研究対象としており、認定事実を問題にしない研究姿勢であることが、長く、裁判官・裁判所のデタラメ事実認定を放置してきました。日本の法学者が、法律事件にコメントを出さない風習はこのようにして形成されてきたのです。
しかも性質がわるいことに、日本の法学者は、学者裁判官として最高裁判所の裁判官になることが「双六の上り」と思っており、「至上の名誉」とあこがれています。そうでなくとも、法学教育者として最高裁から弁護士資格を認定されることを余生の楽しみとしています。
もはや、日本の法学者で最高裁を批判する者は皆無といっても過言ではありません。例外的に学者で最高裁を批判するのが、瀬木比呂志氏ですが、氏は裁判官退任者であり、身内のえげつなさにたまらず学者となって批判者となった人です。
学者が実務を知らない例として1つの体験を述べておきます。それは、裁判手続に期限が故意に設定されていないことです。国民の失権規定としての期限規定は無数に存在しますが、肝心の裁判官の応答義務としての判決期限規定は存在しません。このため、裁判官は判決期日を自由自在に設定します。このため、裁判は一般に長期を要します。時には裁判官の交代移動時期を見据えて、判決をしないこともあります。これは明らかに国民の迅速な裁判を受ける権利(憲法第37条では刑事裁判について迅速裁判請求権の明文規定が存在します。もちろん、民事裁判は迅速の必要がないとする合理的根拠はありません)を侵害していますが、憲法上に明文規定がないため、学者や専門家は議論すらしません。
迅速裁判を保障する法技術は判決期限を法定することで簡単に達成できることです。「慎重な審議のため時間がかかる」というのは裁判を体験する限り、真っ赤な嘘です。司法試験合格者は膨大な法律問題を瞬時に正しく判断決断する技術が必要です。これも体験的真実です。
少し専門的な議論となりますが、裁判所は「法律上の争訟」しか裁判の対象としません。
従って、まず裁判官は事件の申立てが、裁判の対象としての要件を充たしているかどうかを審理します。これを「要件審理」といって、「本案審理」と区別しています。要件審理は本案前審理ですから、ここで裁判手続が拒否されれば、門前払いとなります。この門前払い論理の当否の最終判断は最高裁の判断に関する限り存在しません。これが最高裁を神の存在としている1つの理由です。もちろん、本案判決についても最高裁判決の誤謬を訂正する仕組みは存在しません。代理人の過誤は本人が修正訂正する他ないのですから、不当な最高裁判所の判決に対して、国民が直接それを是正する手段方法が必要です。
少なくとも国民は選挙によって、最高裁裁判官を選任することができるとすべきでしょう。刑事裁判の裁判員は無作為による一般市民からの選任ですが、最高裁の裁判官こそ、一定の裁判員を国民が直接選任できるようにしなければ、司法の腐敗の根絶はできません。
(つづく)
関連記事
2024年4月8日 14:102024年4月3日 15:002024年4月1日 17:002024年4月25日 14:002024年4月15日 17:202024年4月5日 17:402024年4月25日 14:00
最近の人気記事
週間アクセスランキング
まちかど風景
- 優良企業を集めた求人サイト
-
 Premium Search 求人を探す
Premium Search 求人を探す
- 業界注目!特集
-
 産廃処理最前線
産廃処理最前線
サステナブルな社会を目指す
- MAX WORLD監修
-
 パーム油やPKSの情報を発信
パーム油やPKSの情報を発信
パームエナジーニュース







 自由心証権とは裁判官に証拠の評価について自由な裁量権を認めた訴訟法レベルの規範です。この規定によって裁判官が自由に証拠の評価をすることは、正に法律の規定に従っているという意味では外形的・形式的には「適正手続」です。しかし、証拠の評価は科学的で合理的なものでなければならず(証拠裁判主義)、裁判官が自由に心証で評価できるという規定自体が、非科学的で不合理です。これは裁判官を神として認めるようなもので、日本司法の冤罪・誤判の根本原因です。
自由心証権とは裁判官に証拠の評価について自由な裁量権を認めた訴訟法レベルの規範です。この規定によって裁判官が自由に証拠の評価をすることは、正に法律の規定に従っているという意味では外形的・形式的には「適正手続」です。しかし、証拠の評価は科学的で合理的なものでなければならず(証拠裁判主義)、裁判官が自由に心証で評価できるという規定自体が、非科学的で不合理です。これは裁判官を神として認めるようなもので、日本司法の冤罪・誤判の根本原因です。